▶︎財務指標に対してのマーケターとしての貢献
マーケターもマーケティング活動を行う際に、ここまでお話してきた3つの主要財務指標(ROE、ROIC、PBR)を向上させることを意識する必要があります。現在の事業がしっかりと結果を出すことと並行して、将来の稼ぐ力を訴求するためのマーケティング活動が余儀なくされます。
特に忘れてはいけないのが、投資家(とくに機関投資家)が、投資を決める際にもっとも重要視しているのが「企業の未来の稼ぐ力」だという点です。投資家、特にL.O(Long Only)やエンゲージメントファンドに分類される投資家から経営者へ期待することは3つ、
1.大型M&Aなどによる事業ポートフォリオの入れ替え(PER)
2.価格戦略(ROE)
3.ビジネスモデル強化(ROE&PER)
です。
加えて昨今は、「無形資産の重要性」が頻繁に叫ばれるようになってきました。
▶︎有形資産 v.s. 無形資産
現代の経済活動において、企業価値と競争優位性の源泉が有形資産(工場、設備、土地など)から無形資産(ブランド、技術、人材、データなど)へとシフトしていることを背景に、企業にとっての無形資産の重要性が極めて高まっています。無形資産には3本柱があります。それは「ブランド」「人的資本」「知的財産」の3つです。
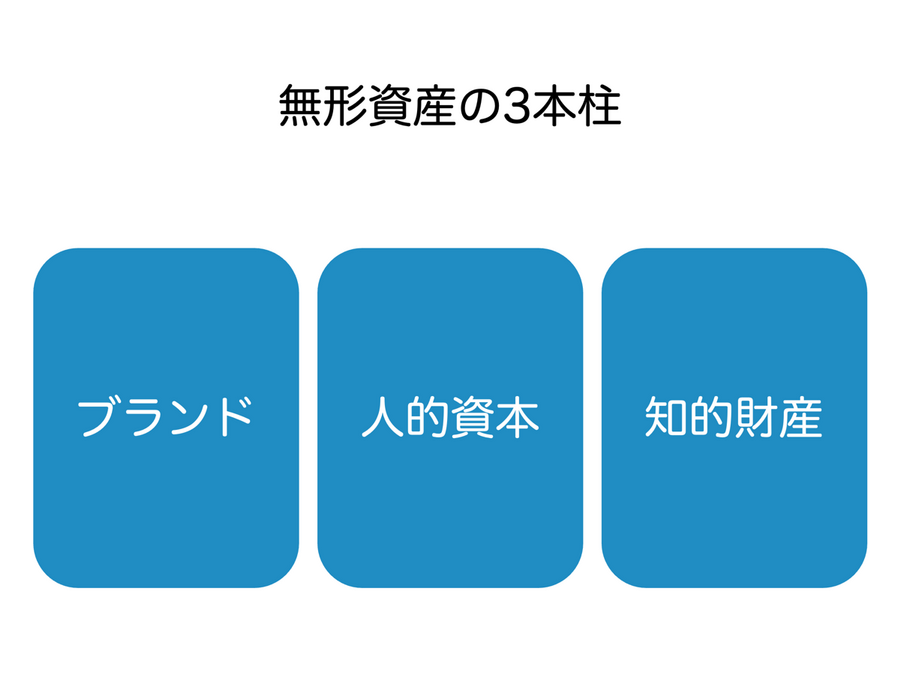
かつて企業価値の多くは工場や機械設備といった有形資産で構成されていましたが、デジタル化とグローバル化が進んだ現代では、目に見えない資産こそが収益力と成長を決定づけるものとして見られるようになってきました。
特にハイテク企業やプラットフォーム企業では、時価総額に占める無形資産の比率が非常に高くなっています。独占的な競争優位性を担保する 特許、商標、意匠、独自のソフトウェア、顧客データ、ノウハウ、長年にわたって築かれたブランド力などは、他社が容易に模倣できない独自の強みとなり、価格競争に巻き込まれずに利益を上げ続ける源泉となるからです。例えば、イノベーションを促進させるための研究開発(R&D)によって蓄積された技術やノウハウ、優れた組織文化は、新しい製品やサービスを生み出すイノベーションの基盤となります。
さらに人的資本(Human Capital)の重要性の高まりも見逃せません。「従業員こそが最大の資本」として、無形資産のなかでも、従業員が持つスキル、知識、経験、チームワークといった人的資本は最も重要な要素の一つになってきました。優秀な人材への投資(研修、働きやすい環境、エンゲージメント向上など)は、生産性の向上や新しい価値創造に直結します。さらに、持続的な成長力を担保するためには、変化に対応できる柔軟な組織と、それを支える従業員の能力が不可欠です。人的資本への投資は、将来の利益を生み出すための「資本」とみなされるようになってきました。国際標準規格のISO30414や今年公表されたISO30201に代表されるように、この領域の環境も整いつつあります。
企業価値評価の視点として、投資家や市場も企業の財務諸表に計上される有形資産だけでなく、将来のキャッシュフローを生み出す無形資産を重視し始めています。
PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)との関係では、企業がブランドや技術といった無形資産を強化し、それらを活用することで高いROEを安定的に達成できれば、市場からの評価が上がり、PBRの上昇につながります。
最近では、株主や投資家から非財務情報の開示要求が強くなってきていますが、残念ながら無形資産の多くは会計上の貸借対照表に計上されません。そのため投資家は、企業に対して統合報告書などを通じて研究開発投資、人的資本投資、サステナビリティ(ESG)への取り組みといった「非財務情報」を積極的に開示し、長期的な価値創造戦略を説明するよう求めています。
皆さんの企業の経営層はこの無形資産に関しての感度はいかがでしょうか?「目に見えないものが大切」だということに腹落ちしているでしょうか?私が認識している限り、かつて日本の上場企業は、上場しているにも関わらず、資金調達において直接金融ではなく、間接金融に頼っていました。
資金の流れ方によって金融システムは2つの方法があります。資金の出し手(投資家)と受け手(企業や国)が、金融機関を介さずに株式や債券などの金融商品を直接やり取りして資金を融通する直接金融と、資金の出し手と受け手の間に銀行などの金融機関が介在し、金融機関が仲介役となって資金を融通する間接金融です。
昭和の時代、上場しているにも関わらず銀行などの金融機関から資金を調達するケースが主流を占めていた企業では、無形資産には金融機関から資金を借り入れるための担保価値としては扱われることがないため、担保価値のある有形資産に意識が引っ張られます。もちろん「目に見えない」資産ということもありますが、日本の経営者がなかなか無形資産に馴染めない背景にはこのこともあるかも知れません。このような状況では、投資家から評価される「未来の稼ぐ力」を彷彿させる企業として認知されることは難しく、企業価値向上には大きな課題となっているのではないでしょうか。
私が冒頭で「マーケターの貢献」を示させてもらったのは、まさにこの企業価値向上のために、「無形資産」である「非財務」を「未財務」として、企業価値向上に向けてのマーケティング活動を実施されることをお勧めしたいからです。
もう一度思い出してください。無形資産の3本柱は「ブランド」「人的資本」そして「知的財産」です。ブランド力向上はまさにマーケターの重要な貢献目標ですね。いかに企業ブランドを向上させ、顧客だけではなくすべてのステークホルダーのブランド想起を確たるものにしていくか。特に重要なことは、社外のステークホルダーよりも、最も優先度を上げて対処すべきは社内のステークホルダー、そうです「従業員」に対するインナーブランディング活動の強化になります。
「人的資本」はどうでしょう?一見、マーケティングとは直接関係のない対象に思われがちですが、実は「マーケティング」と「人的資本」は、抜群の相性です。なぜなら、どちらも基本は「人を知ること」だからです。人的資本戦略にもマーケティング・マインドがとても有効に機能します。
3本柱の中で、もっとも範囲も広く、奥も深いのが、「知的財産」です。特許や商標、さまざまな社内ノウハウ、顧客やサプライヤーなどなど、挙げればキリがありませんが、この領域においてもマーケティング・マインドが威力を発揮します。
後編に続く
マーケターもマーケティング活動を行う際に、ここまでお話してきた3つの主要財務指標(ROE、ROIC、PBR)を向上させることを意識する必要があります。現在の事業がしっかりと結果を出すことと並行して、将来の稼ぐ力を訴求するためのマーケティング活動が余儀なくされます。
特に忘れてはいけないのが、投資家(とくに機関投資家)が、投資を決める際にもっとも重要視しているのが「企業の未来の稼ぐ力」だという点です。投資家、特にL.O(Long Only)やエンゲージメントファンドに分類される投資家から経営者へ期待することは3つ、
1.大型M&Aなどによる事業ポートフォリオの入れ替え(PER)
2.価格戦略(ROE)
3.ビジネスモデル強化(ROE&PER)
です。
加えて昨今は、「無形資産の重要性」が頻繁に叫ばれるようになってきました。
▶︎有形資産 v.s. 無形資産
現代の経済活動において、企業価値と競争優位性の源泉が有形資産(工場、設備、土地など)から無形資産(ブランド、技術、人材、データなど)へとシフトしていることを背景に、企業にとっての無形資産の重要性が極めて高まっています。無形資産には3本柱があります。それは「ブランド」「人的資本」「知的財産」の3つです。
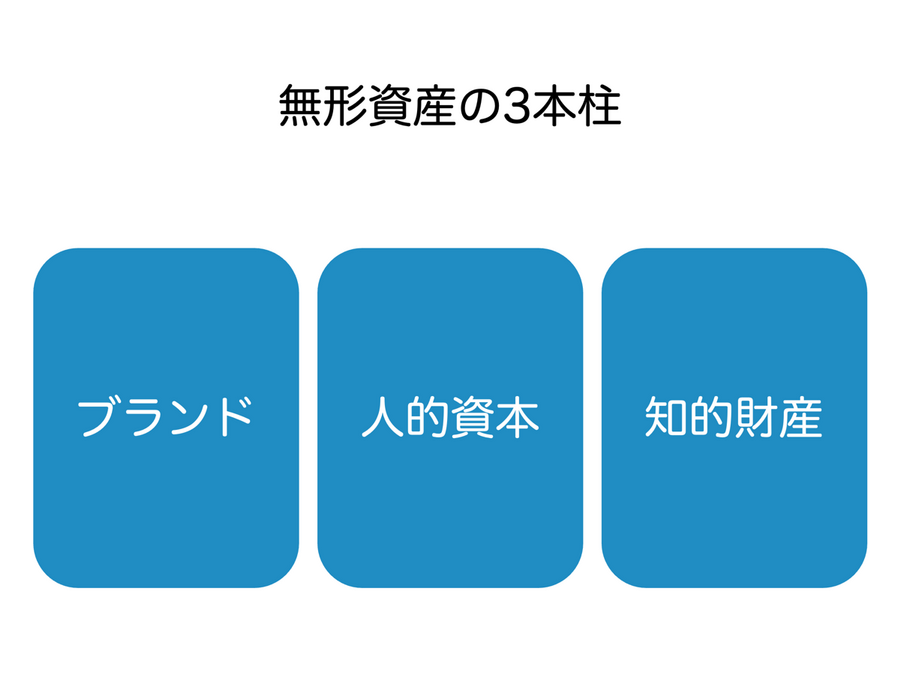
【企業価値の源泉の変化と競争優位性の確立】
かつて企業価値の多くは工場や機械設備といった有形資産で構成されていましたが、デジタル化とグローバル化が進んだ現代では、目に見えない資産こそが収益力と成長を決定づけるものとして見られるようになってきました。
特にハイテク企業やプラットフォーム企業では、時価総額に占める無形資産の比率が非常に高くなっています。独占的な競争優位性を担保する 特許、商標、意匠、独自のソフトウェア、顧客データ、ノウハウ、長年にわたって築かれたブランド力などは、他社が容易に模倣できない独自の強みとなり、価格競争に巻き込まれずに利益を上げ続ける源泉となるからです。例えば、イノベーションを促進させるための研究開発(R&D)によって蓄積された技術やノウハウ、優れた組織文化は、新しい製品やサービスを生み出すイノベーションの基盤となります。
さらに人的資本(Human Capital)の重要性の高まりも見逃せません。「従業員こそが最大の資本」として、無形資産のなかでも、従業員が持つスキル、知識、経験、チームワークといった人的資本は最も重要な要素の一つになってきました。優秀な人材への投資(研修、働きやすい環境、エンゲージメント向上など)は、生産性の向上や新しい価値創造に直結します。さらに、持続的な成長力を担保するためには、変化に対応できる柔軟な組織と、それを支える従業員の能力が不可欠です。人的資本への投資は、将来の利益を生み出すための「資本」とみなされるようになってきました。国際標準規格のISO30414や今年公表されたISO30201に代表されるように、この領域の環境も整いつつあります。
【投資家からの評価基準の変化】
企業価値評価の視点として、投資家や市場も企業の財務諸表に計上される有形資産だけでなく、将来のキャッシュフローを生み出す無形資産を重視し始めています。
PBR(株価純資産倍率)・ROE(自己資本利益率)との関係では、企業がブランドや技術といった無形資産を強化し、それらを活用することで高いROEを安定的に達成できれば、市場からの評価が上がり、PBRの上昇につながります。
最近では、株主や投資家から非財務情報の開示要求が強くなってきていますが、残念ながら無形資産の多くは会計上の貸借対照表に計上されません。そのため投資家は、企業に対して統合報告書などを通じて研究開発投資、人的資本投資、サステナビリティ(ESG)への取り組みといった「非財務情報」を積極的に開示し、長期的な価値創造戦略を説明するよう求めています。
皆さんの企業の経営層はこの無形資産に関しての感度はいかがでしょうか?「目に見えないものが大切」だということに腹落ちしているでしょうか?私が認識している限り、かつて日本の上場企業は、上場しているにも関わらず、資金調達において直接金融ではなく、間接金融に頼っていました。
資金の流れ方によって金融システムは2つの方法があります。資金の出し手(投資家)と受け手(企業や国)が、金融機関を介さずに株式や債券などの金融商品を直接やり取りして資金を融通する直接金融と、資金の出し手と受け手の間に銀行などの金融機関が介在し、金融機関が仲介役となって資金を融通する間接金融です。
昭和の時代、上場しているにも関わらず銀行などの金融機関から資金を調達するケースが主流を占めていた企業では、無形資産には金融機関から資金を借り入れるための担保価値としては扱われることがないため、担保価値のある有形資産に意識が引っ張られます。もちろん「目に見えない」資産ということもありますが、日本の経営者がなかなか無形資産に馴染めない背景にはこのこともあるかも知れません。このような状況では、投資家から評価される「未来の稼ぐ力」を彷彿させる企業として認知されることは難しく、企業価値向上には大きな課題となっているのではないでしょうか。
私が冒頭で「マーケターの貢献」を示させてもらったのは、まさにこの企業価値向上のために、「無形資産」である「非財務」を「未財務」として、企業価値向上に向けてのマーケティング活動を実施されることをお勧めしたいからです。
もう一度思い出してください。無形資産の3本柱は「ブランド」「人的資本」そして「知的財産」です。ブランド力向上はまさにマーケターの重要な貢献目標ですね。いかに企業ブランドを向上させ、顧客だけではなくすべてのステークホルダーのブランド想起を確たるものにしていくか。特に重要なことは、社外のステークホルダーよりも、最も優先度を上げて対処すべきは社内のステークホルダー、そうです「従業員」に対するインナーブランディング活動の強化になります。
「人的資本」はどうでしょう?一見、マーケティングとは直接関係のない対象に思われがちですが、実は「マーケティング」と「人的資本」は、抜群の相性です。なぜなら、どちらも基本は「人を知ること」だからです。人的資本戦略にもマーケティング・マインドがとても有効に機能します。
3本柱の中で、もっとも範囲も広く、奥も深いのが、「知的財産」です。特許や商標、さまざまな社内ノウハウ、顧客やサプライヤーなどなど、挙げればキリがありませんが、この領域においてもマーケティング・マインドが威力を発揮します。
後編に続く




 メルマガ登録
メルマガ登録


