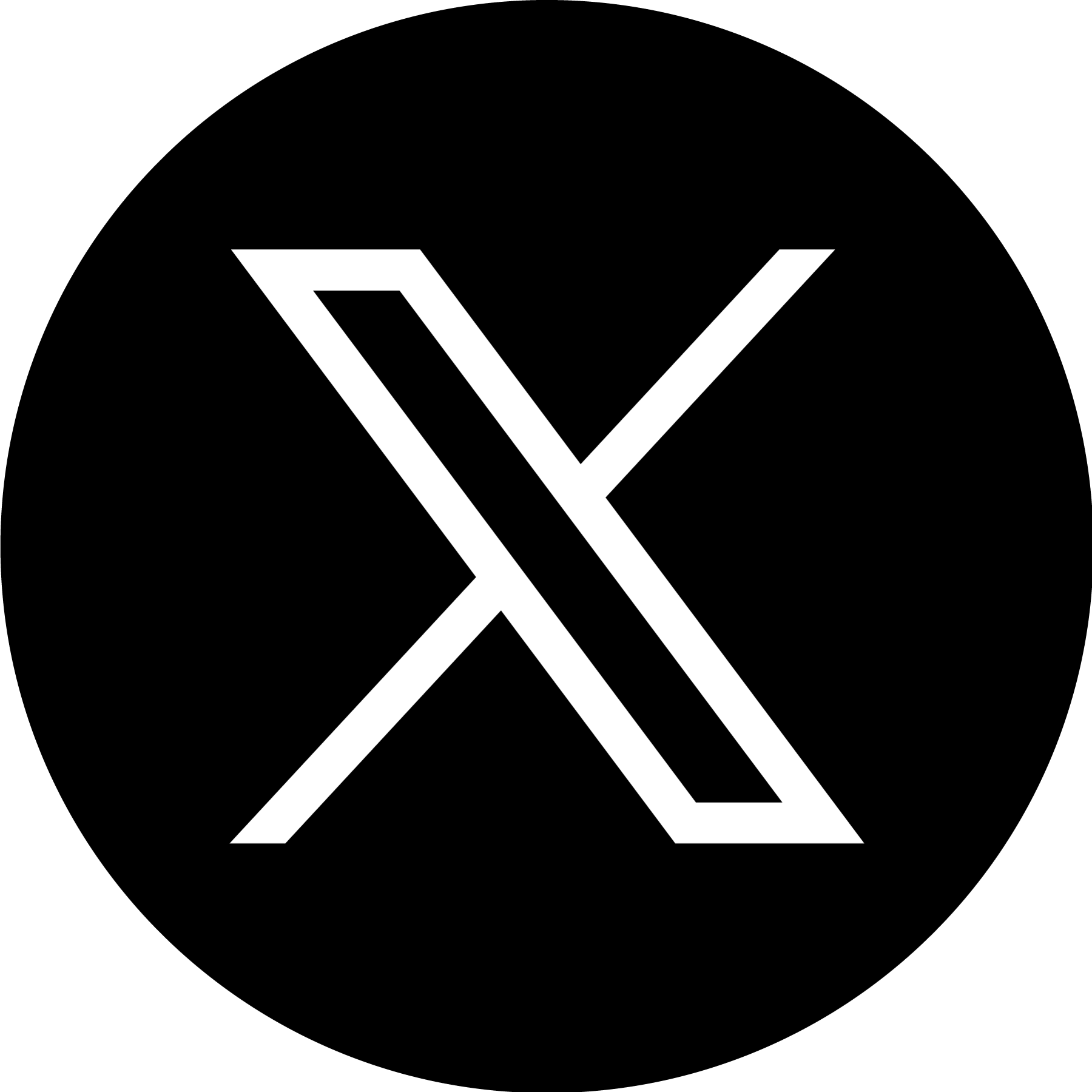本田哲也、藤原義昭 特別対談 #02
「ナラティブでなければ、顧客からも従業員からも選ばれない」 本田哲也、藤原義昭 特別対談
潜在的に企業に眠るものを言語化することがパーパス
――従業員が権限を与えられた時、自らの行動が正しいのかを企業理念のもと自ら判断していけるといいですね。
本田 それが理想的な形です。だから、パーパスも大事になってくるんですよね。ただ、パーパスをつくることが目的になってしまっている企業もあるんです。
それにパーパスの策定はゼロからつくるようなものではなく、企業に潜在的に持っているものをもう一度、言語化しようというプロセスです。また、パーパスが言語化されるだけで、その先を考えていない企業もあります。
ナラティブの実践とは、パーパスを実装するためのひとつのステップであり、その策定が目的になってはいけないんです。
藤原 目的と手段が途中で入れ変わってしまうことは、よくありますよね。
本田 はい。経営層からすると、ESG経営も意識しなければいけないし、大変な時代なんですよね。特に経営者の代替わりも起こっているタイミングなので、これまでにない中期経営計画の発表をしなけければという思いもあるでしょう。
新たに就任した経営者にとって、「パーパスの発表」は分かりやすいし、ステークホルダーの指示も得やすいんですよね。
藤原 変えたという、言い訳にもできますし。
本田 それから、ナラティブはスタートアップ企業でも重要ですが、パーパスが暗黙知として機能している30人程度の組織だと、あまりパーパスを言語化する必要がないんですよね。どちらかと言えば、企業規模が大きくなるにつれて、社員やステークホルダーにそれ(パーパス)が伝わりにくくなる傾向があるので、そこでパーパスの可視化が必要になるのですね。
突破口は、斬新さではなく基本にある
――コロナ禍では、お客さま自身が自分にあったサービスを探しはじめるなど、ますます行動が早くなっていますよね。本田 実はお客さまの方が企業のことを理解しているのではないかと思うことがあります。地方の話ですが、30代から40代の2代目社長が事業を時代に合わせて変えなければならないと迷走して、創業時の理念を否定しようとすることがあります。
そういう経営者の間違った考えを正してくれるのは、地方ではお客さまだそうです。実は地方企業のほうがナラティブな共創構造ができているのでは?という仮説を持っています。
藤原 地方企業は、言語化していないだけで、ナラティブが実行できている企業はたくさんあると思います。
本田 「言語化しよう」とも思っていないですよね。地方独特の背景やカルチャーを含めて、そのエコシステムの中にいると見えないけれど、脈々と物語構造ができ上がっているんだなと感じることがあります。
最先端と呼ばれるD2Cのモデルと地方企業には、実は共通性があるのではないかとすら思っています。
藤原 地方に行くと、同じ饅頭を50年間食べている人もいますよね。
本田 そうなると、もはや饅頭屋という企業と消費者としてのお客さまとの関係ではないですよね。その饅頭は、そのお客様の家庭での「物語」の一部になっているかもしれない。そこには、ナラティブ戦略やナラティブマーケティングという言葉は、存在さえしていないはずです。

藤原 企業側は、自分たちがお客さまに提供している価値を明確に知らないことに気づかされますね。すごく良いものを持っているのに、それが当たり前すぎて、自分ではその凄さに気付いていないんです。
ただ、D2C企業は自分たちの価値をずっと問い続けることで、うまく顧客とコミュニケーションできていると思うんです。
本田 得てして、突破口になるのは、斬新なことではなく基本的なことなんですよね。
藤原 その通りですね。私がユナイテッドアローズに入社して衝撃的だったのは、新商品を展開したタイミングで実店舗を見に行ったのですが、その商品が陳列されていなかったんです。
それで理由を聞いたら、「アイロン掛けが甘いから回収した」と平気で言うんです。在庫が大量にあっても、絶対にそのままでは販売しようとしません。
ブランドとして仕立てにこだわりがあるからこそ、商品を回収してプレスをし直すことを決めているわけです。これこそが自分たちの強みだなと気づかされました。
本田 まさに企業には、そういうエピソードが眠っているんです。なぜそれが必要かを深掘りするとパーパスに繋がったりして、単なるエピソードからダイナミックな物語が見えてきます。細部にこそ、「ナラティブ」が宿っているのです。


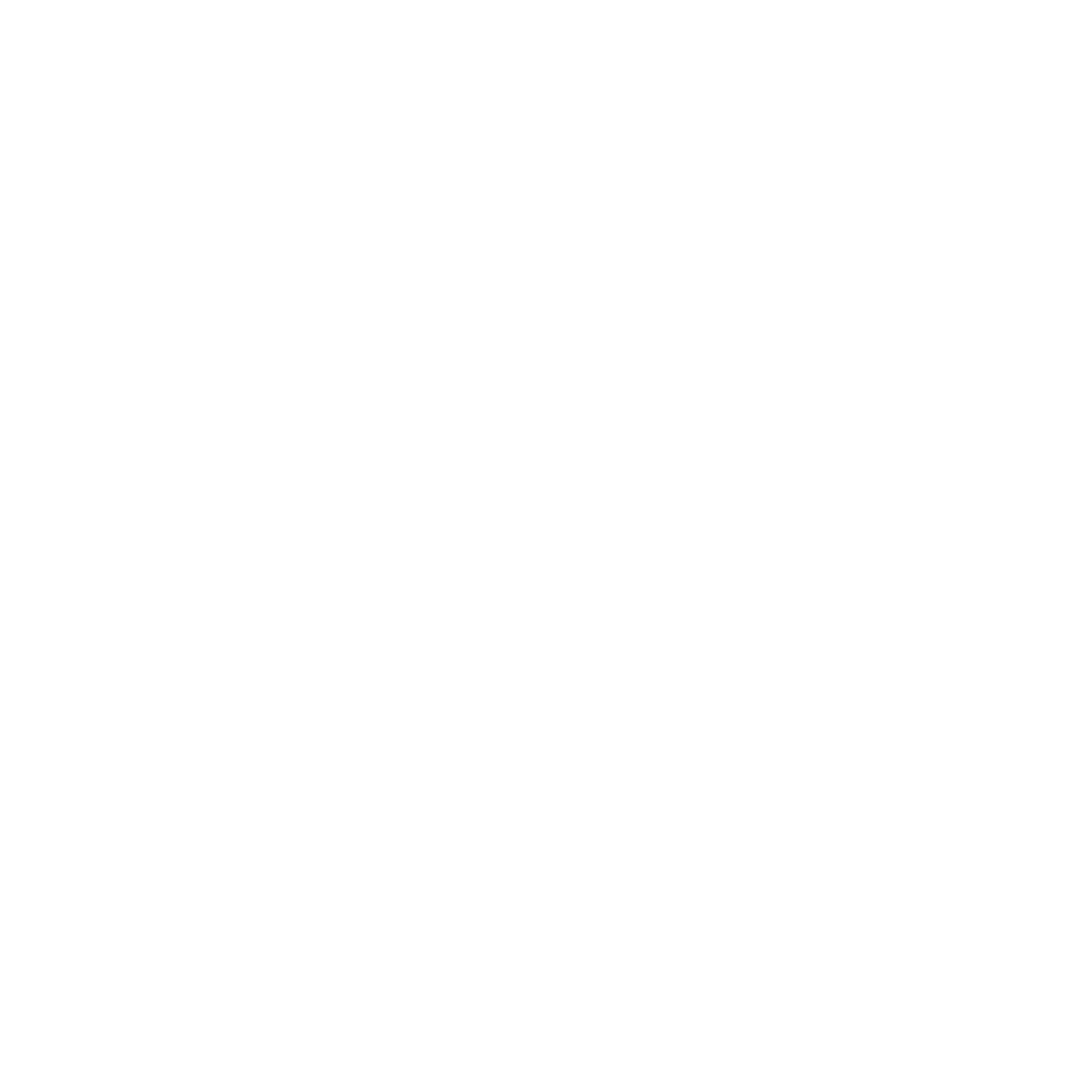

 メルマガ登録
メルマガ登録