【読書の秋】視野が広がった、視座が上がった、視点が増えた1冊 #11
資生堂ジャパン 清水明子氏、ポーラ 中村俊之氏の「視野が広がった、視座が上がった、視点が増えた1冊」
2025/11/13
資生堂ジャパン クレ・ド・ポー ボーテ事業部 マーケティング ヴァイスプレジデント 清水明子氏
『ストーリーとしての競争戦略』
楠木健(著)、東洋経済新報社
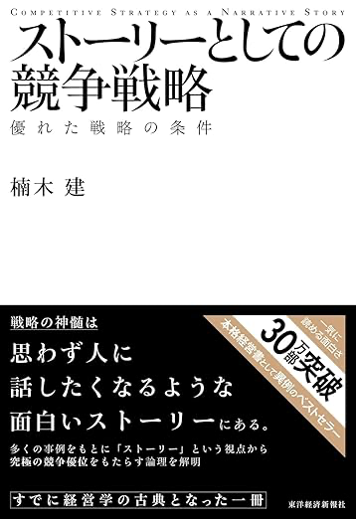
今となっては人生の大きな分岐点のひとつだったと思える、別名「隔離されたクレイジー・ユートピア」と名の付くユニーク極まりない高校に入学することが出来たのは、当時アガサ・クリスティが好きだったからだ。
先生達の趣味としか思えない毎年の入試問題で、その年の英語の試験問題は殺人事件のストーリーを読ませた上で犯人が誰かを論じよ、というものだった。「アガサ・クリスティ好き」だったが故にトリックが一瞬で解けて犯人を特定することが出来、当時憧れて止まなかった高校へと進学した。
この時の「アガサ・クリスティ」のように、自分が持っている「ふとしたもの」が全く別の文脈で役割発揮をしてリソースに転換されて扉が開き、その後更に人生の別の体験へと繋がった経験は、「市場を俯瞰してリソースとなり得そうなものを探す」マーケッターとしての起点を創る「点」だったのかも知れない。
ビジネスにおいては日々市場や競合環境が変化する中で、どんなに美しくプランを描いてもその通りに行かぬことばかりの中、逆に注目もしていなかった事が後にブランドのリソースとして活用できることがある。匍匐前進で日々の売り上げと格闘をしていると市場が変わっているのに最初に描いたプランの推進にそのまま邁進してしまい、自ブランドのリソースを俯瞰で見て見つめなおすということを忘れがちだが、この本は意図せず苦肉の策として「それしかなくて置いた」駒が、その後競合に対する圧倒的な競争優位を確立するようになる戦略展開がライブ感溢れる「戦略ストーリー」として語られる。
「点」を「線」として繋げ、他社が気づいた時には追いつくことが出来ないブランドの圧倒的な強みへと発展していく事例が共有され、「ユニークネス」が時間と共にどんどん強固な「競争優位」へと発展する様を論じる著者の戦略解説は、まるでミステリー小説を読んでいるかのようなドラマティックな「ストーリー」となっている。
フレームワークとテンプレート、勝ち筋のパターン化流行りの世の中において、マーケティングは「予定通りに行かない」からこそ面白いと思っている。他社と比較し、betterを探すのではなく、「他社との違いをどんどん太く強くする」。その過程において、最初のプランに固執し、視野を狭く閉じて競合ベンチマークをするのではなく、手元にあるキラキラと輝く「自ブランドだけの」宝物としてのリソースを発掘し、「太く強いストーリー」に変えることで沢山のユニークなブランドが世に出ることを願っている。
ポーラ EC事業部長 中村俊之氏
『誰も教えてくれなかったジャズの聴き方: Jazz bible』
水城雄 (著) 、ブックマン社
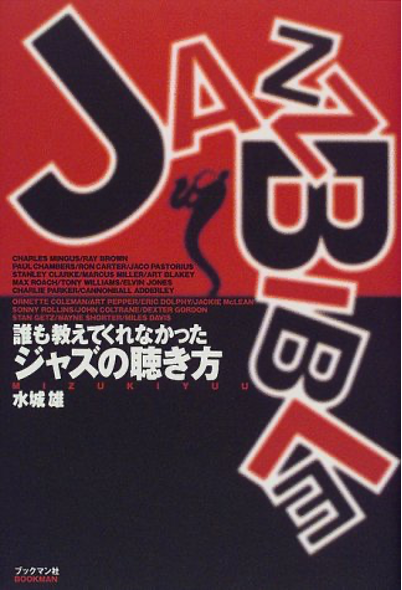
事業運営から目の前の小さなタスクまで、構造的にものごとをとらえた効率的・効果的な判断とマネジメントの実践を志向する一方で、誰かの心揺さぶるような仕事をしたいと思うほどに、創造性や生々しさに繋がる 「余白」について考えさせられます。
本書との出会いは新規事業を立ち上げていた20代、フレームワークやプロジェクトマネジメントを学びたてで、少し得意げになっていた時期でした。好きな音楽にジャズをサンプリングしたものが多く、一度ちゃんと聴いてみたいなと思い入門書として手に取りましたが、結果としてジャズの魅力と深さを知ると同時に、自分は型に溺れた企画づくりやプロジェクト推進をしていると気付かされた1冊でした。
「ジャズは難しそうで敷居が高い 」という当時の私と同じ印象の方もいらっしゃるかもしれませんが、本書は「そもそもジャズとは何か」「アドリブとは何か」といった素朴な疑問について分かりやすく解説してくれます。また楽器や奏法、ジャズジャイアンツや楽曲の具体事例を交えながら、ジャズピアニストで小説家でもある著者が、自身の言葉でジャズの魅力を語りかけてくれるので、楽器の弾けない私ですら、まるでその音の中に存在しているような感覚を得られました。
整理された情報を正義とし、フレームワークに言葉を埋めることが仕事であると思い込んでしまっていた当時の私に鳴らされた警笛のように感じたことを、今でも覚えています。難しいテーマを構造的に分かりやすく解説するだけでなく、新しい世界の扉の一歩先まで伴走してくれるような本書の体験を通じて、企画書に書かれた退屈な文言や、本質を理解していれば避けられた判断ミスの原因を指摘されているようでした。当時の私は型に溺れて、誰かにとっての価値をつくる・高めるという本来の目的を見失い、創造や発想の可能性をふさいでいたのだと思います。
また、素人の私が語るにはおこがましいので深くは触れませんが、コード進行という規律と瞬発的な創造性が生むインプロビゼーション(即興)というジャズの魅力を知れたことも、大きな気づきのきっかけとなりました。
まえがきにあるジャズとたわむれられる自身を「幸せだ。」と表現する著者の言葉が入口となり、読み終えるころには入門書や解説書といった枠を超えた価値を生み出している書籍だと思います。本書から「規律とゆらぎ」の大切さを学び、それは今の私の仕事のスタイルをつくった大切なキーワードとなっています。
※編集部注:記事内で紹介した書籍をリンク先で購入すると、売上の一部がAgenda noteに還元されることがあります。




 メルマガ登録
メルマガ登録























