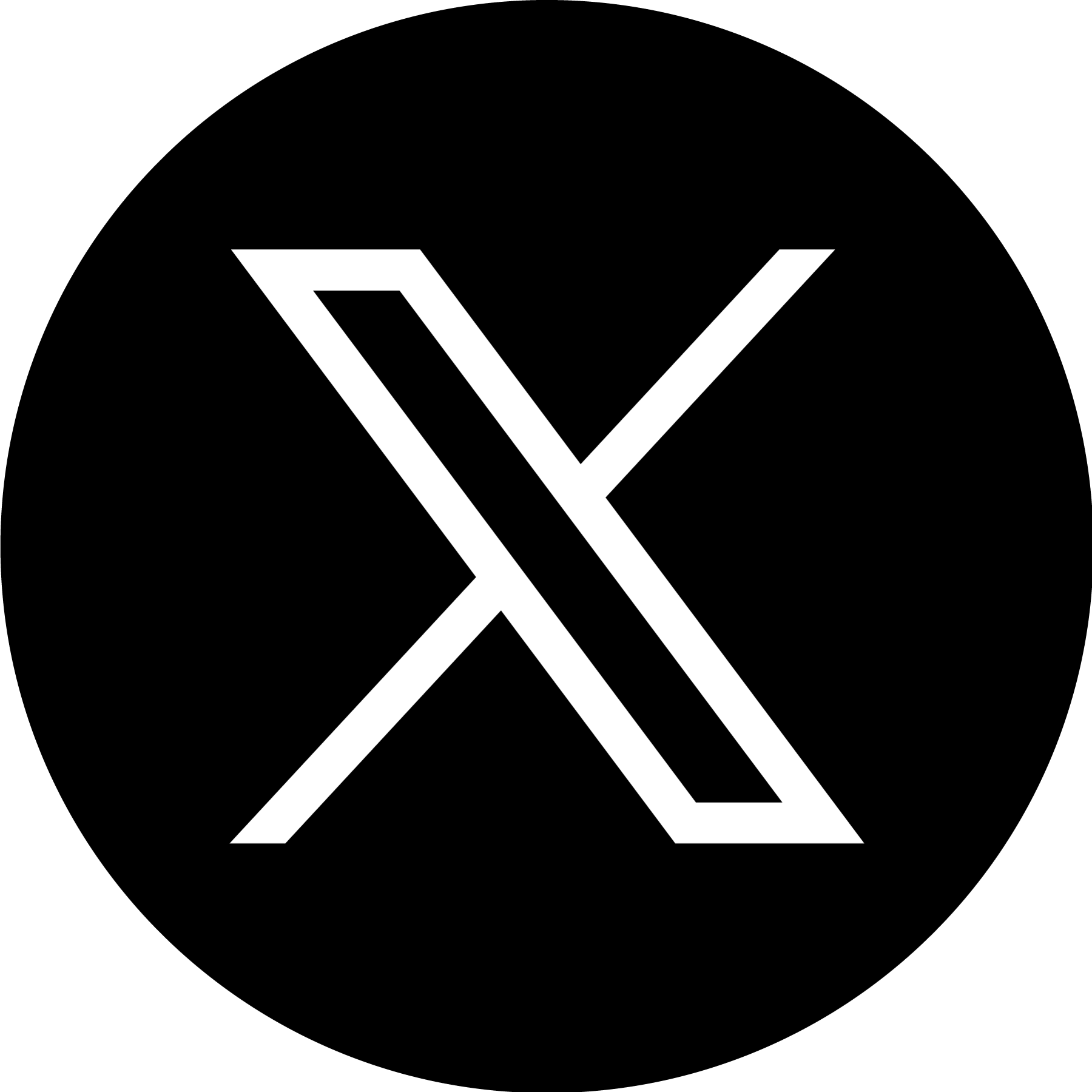マーケティング・ビジネス課題を解決する学術研究 #09
巨大プラットフォームに乗ってしまっていいのか? 経営学者たちの「6つの提言」から採るべき方向を見定める
2026/01/19
マーケティングやビジネスの最新情報を得るには、実証された知見が多く詰まっている研究者の学術研究にも目を向けることが重要になる。早稲田大学ビジネススクールの客員教授である及川直彦氏による本連載では、マーケティングや営業、新規事業開発に携わるビジネスパーソンが直面する課題に対し、学術的な視点から解決策を提供していく。
今回のテーマは「プラットフォームとの向き合い方」。企業活動においてプラットフォームの存在感が高まる中、支配的な巨大プラットフォームを利用することはさまざまなメリットがある一方でコモディティ化など深刻なリスクもある。企業はどのようにプラットフォームと向き合うべきなのか。プラットフォームの本質を知り、現実的で有効な戦略をとるための手がかりとなる議論と具体的な提言を、及川氏が独自の観点から紹介・考察する。
今回のテーマは「プラットフォームとの向き合い方」。企業活動においてプラットフォームの存在感が高まる中、支配的な巨大プラットフォームを利用することはさまざまなメリットがある一方でコモディティ化など深刻なリスクもある。企業はどのようにプラットフォームと向き合うべきなのか。プラットフォームの本質を知り、現実的で有効な戦略をとるための手がかりとなる議論と具体的な提言を、及川氏が独自の観点から紹介・考察する。
背景に「情報集約度」の高まり
ビジネススクールの学生には、日本を代表する大企業で活躍する人が多いのですが、私の担当する授業が「デジタル・イノベーションとマーケティング」というタイトルであることもあり、授業後の懇親会などで、そのような人たちから最も多く質問されることのひとつが、「テック企業が提供するプラットフォームに、自分たちの会社は乗ってしまってもいいのだろうか。どう向き合うべきなのだろうか」というものです。
こういった質問は、メディアビジネスや広告ビジネスのような、製品・サービス自体において情報集約度が高い*ビジネスに携わる人だけでなく、産業財メーカー(例: 製薬や産業機械)や消費財メーカー(例: 化粧品、食品)、伝統的な仲介サービス(例: 不動産、人材紹介)といった、製品・サービス自体の情報集約度は必ずしも高くはないビジネスの人からも聞かれることが多くなりました。
製品・サービスを製造・組成し、提供する活動のプロセスであるバリューチェーンの情報集約度が、購買物流やマーケティング・販売の部分で進んでいることから、より幅広い業界において、「プラットフォームとどう付き合うか」が身近な論点になってきたようです。
このテーマについて、プラットフォームに関する複数の実証的な研究に取り組みながら、プラットフォームの本質は何かを考え、それに対して伝統的なビジネスに携わる人たちがどう向き合うべきかについて提言している経営学者たちがいます。今回は、そういった提言の中で代表的なものを紹介します。
*情報集約度とは、製品やバリューチェーンにおいて「物理的な部分」と「情報処理的な部分」のうち、後者が占める割合を示す概念。経営学者のマイケル・ポーターと大手会計事務所アーサー・アンダーセンのビクター・ミラーが提唱したものです。この概念については「20年で激変した広告業界の情報革命、識者は「2024年 日本の広告費」をどう読み解いた?【早稲田大学ビジネススクール 及川直彦氏】 」で解説しています。
プラットフォームとは何か
プラットフォームについて、経営学者たちは、元々は「二面性プラットフォーム (two-sided platform)」として議論してきました。「二面性プラットフォーム」は、「2つの異なるユーザーグループを結びつけ、両者の取引を容易にするためのインフラとルールを提供する製品やサービス」と定義され、パソコンにおける利用者とアプリケーション開発者の間を仲介するOSや、ゲームにおける利用者とゲーム開発会社を仲介するハードウェア、金融・決済におけるクレジットカード会社などが、その代表例として論じられてきました (Eisenmann et al. 2006)。
その後、経営学者たちの議論の対象は、利用者と販売事業者をつなげる小売・マーケットプレイス(例: Amazon、eBay、Alibaba)や、利用者に検索機能や交流の場を無料で提供し、そこで掲出される広告枠を広告主に販売する検索(例: Google)やソーシャルメディア(例: Facebook)、利用者と遊休資産の保有者の間をつなげるシェアリング・エコノミー(例: Uber、Airbnb)、利用者とコンテンツ制作者をつなぐメディア・コンテンツ配信(例: YouTube、Netflix、Spotify)、利用者とアプリケーション開発者などをつなげるスマートフォンのエコシステム(例: AppleのiPhone、GoogleのAndroid)、あるいは産業機器から得られるデータと、それを分析するアプリケーションや開発者をつなげる産業用IoT(例: GE、Siemens)といったサービスに広がっていきました。
そんな議論の広がりの中で、たとえば検索やソーシャルメディアのように、必ずしも2つのサイドだけではなく、それ以上の異なるタイプの顧客間をつなぐ現実が顕在化してきました。たとえばスマートフォンのエコシステムにおいて、GoogleのAndroidは、利用者とアプリケーション開発者に加え、携帯端末メーカーの間をつないでいます。
こういった現実に呼応するように、経営学者たちも、テック企業などが提供するプラットフォームを、「マルチサイド・プラットフォーム (multi-side platform)」と呼ぶようになりました(Hagiu 2009)。そして、「マルチサイド・プラットフォーム」の定義は、「タイプの異なる顧客同士をつなぐ製品、サービス、技術」と定義され、Eisenmann et al. (2006)の定義に「技術」が追加されました(Hagiu 2009)。
従来型のビジネスが「マルチサイド・プラットフォーム」への対応に失敗した事例として、経営学者たちの議論にしばしば登場するのが、トイザらスのAmazonへの対応の失敗です。トイザらスは当初、自社でオンライン事業を立ち上げようとしたものの、うまくいかなかったため、AmazonのECのノウハウを活用することを選択し、年間5,000万ドル+売上歩合をAmazonに支払い、Amazon内にトイザらスのオンラインショップを構築・運営してもらう契約を締結しました。しかし、その結果、トイザらスは顧客との接点(インターフェース)やデータのコントロール権をAmazonに握られることになり、Amazonという巨大なプラットフォームの中で「コモディティ化」し、多くのベンダーのひとつになってしまったと言われています。
このトイザらスの事例から、テック企業が提供する「マルチサイド・プラットフォーム」を、単なる「オンライン販売のインフラ」という程度の認識で付き合うことに対する危険が指摘され、従来型のビジネスが、こういったプラットフォームとどのように関わるべきかについての議論が活発になりました。
「マルチサイド・プラットフォーム」に代表されるプラットフォームは、従来型のビジネスに比べて「一人勝ち」の状況が生じやすいと言われています(根来 2019)。その背景には、従来のビジネスにおいても見られた「先発優位性」「規模の効果・収穫逓増性」といった要因と、「ネットワーク効果」などプラットフォーム特有の要因の相互作用によって引き起こされるメカニズムがあり、現在、早稲田大学の名誉教授で、名古屋商科大学ビジネススクール教授である根来龍之先生の『集中講義デジタル戦略 テクノロジーバトルのフレームワーク』(日経BP、2019年)に、俯瞰的なフレームワークが提示されていますので、このテーマに興味のある方は読むことをお勧めします。


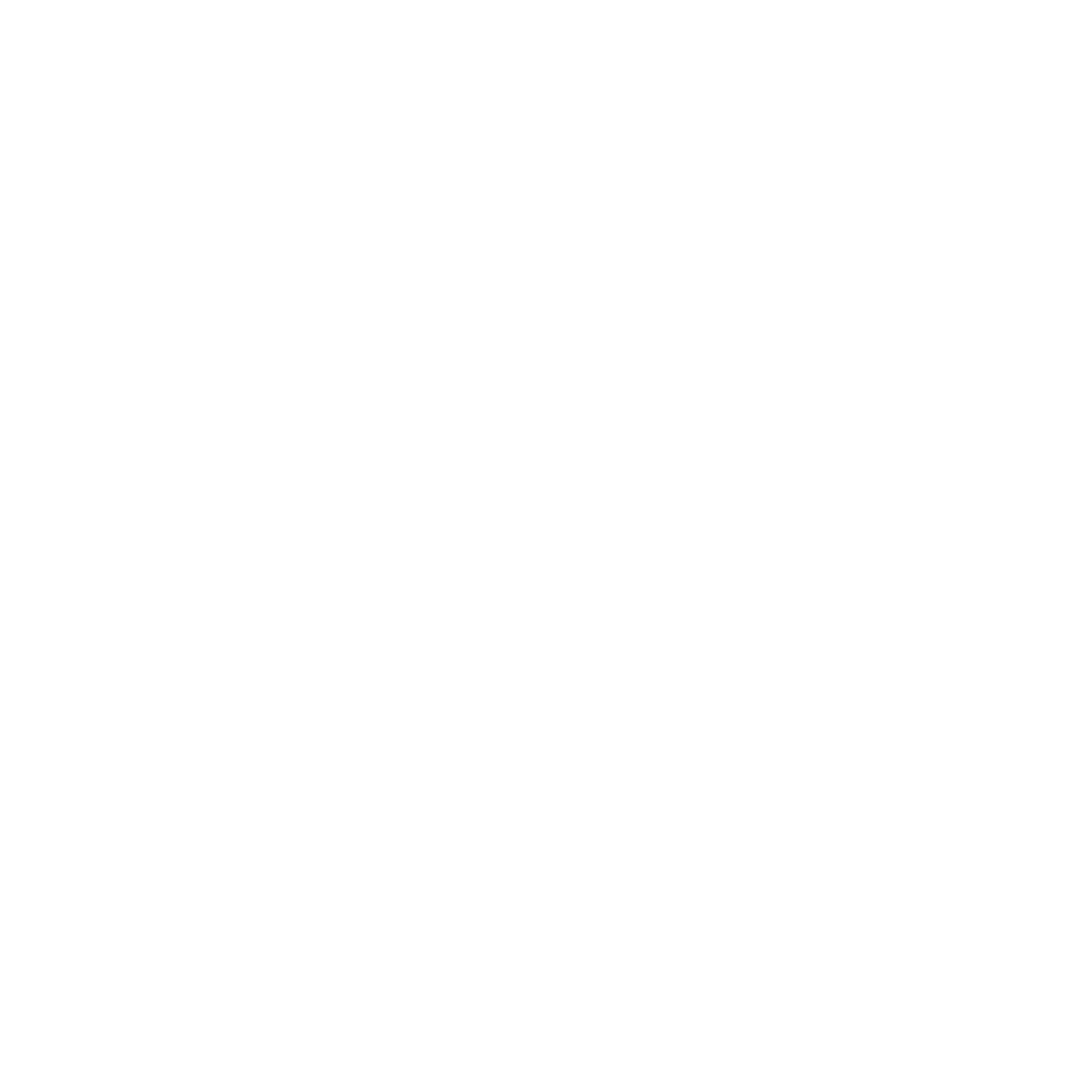

 メルマガ登録
メルマガ登録