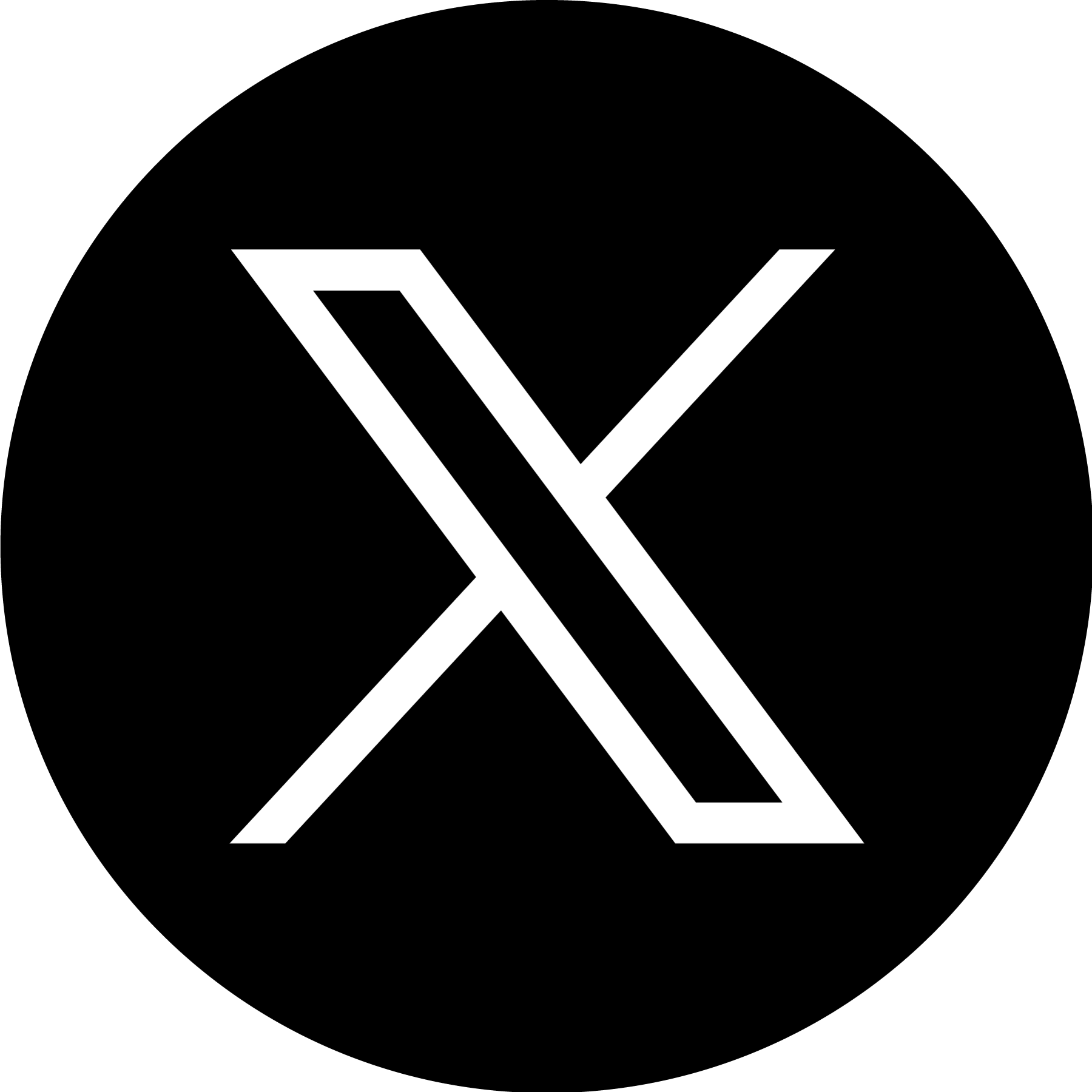SNS・消費行動から見えてくるアラサー女子のココロ #23
すぐに消えるトレンドに疲弊するのはやめよう。「マイノリティデザイン」澤田智洋氏インタビュー
「ゆるスポーツ」生みの親が語る弱さ
Clubhouse(音声SNS)が流行ったと思ったら、数週間後には違う招待制のアプリが話題になっていた。Instagramのハッシュタグのトレンドは、毎月変わるそうだ。数カ月前にバズった商品が、スーパーで山積みになっているのを度々見かける。
私たちはトレンドを追いかけるのに日々必死だ。それは、さまざまな企業の仕事にも同じことが言えるかもしれない。SnapChatが流行ってすぐ、Instagramが「Stories(ストーリーズ)」機能を実装し、今やTwitterにも似たような機能がつけられた。「トレンド」「傾向」「バズ」……、あらわれてはすぐに消えていくものを、血眼になって毎日チェックしているのだ。

「ゆるスポーツ」という名前を聞いたことがある人も多いのではないだろうか。今やさまざまなテレビ番組に取り上げられ、数多くの企業とのコラボレーション企画が生まれ、全国各地で多くの人に親しまれている。
この「ゆるスポーツ」の生みの親である、澤田智洋さんが執筆した書籍『マイノリティデザイン』(ライツ社)がもうすぐ発売される。この本で次々と出てくる、多くの人に愛されているアイデアの出発点は、いずれも「誰かの弱さ」にある。澤田さんは、マイノリティデザインについて次のように話す。
「スポーツが苦手な人がいるということは、世の中で話題にあがるさまざまな社会問題と同じぐらいに重要なテーマではないかと思いました。『自分の弱さ』と聞くと、みなさん大したことがないと思われるかもしれませんが、『社会問題と自分の弱さ、どちらも重要なテーマではないか?』と考えるのが、マイノリティデザインなんです」

トレンドは年々細分化され複雑になり、バズはコモディティ化し、物事のスピードはどんどん速くなって、アイデアが生まれては消えていく。私たちはそんな日々に少々、食傷気味だ。
その一方で、本の中に書かれている「ゆるスポーツ」や、身体障害者を起点につくられた新しい洋服「041FASION」などのアイデアはどれも寿命が長く、プラットフォームのようにひとつのアイデアがさらに別のアイデアを生んでいる。短距離走の繰り返しのような消費社会の中で、どのようにしてまるで「生態系」のように長生きするアイデアがつくれるのだろうか。
「本業はコピーライターなんですけど、ただ、純然たる広告の仕事は今はしていなくて」
そう話す澤田さんが福祉の世界に飛び込んだのは、自分の息子が全盲だったことがきっかけだった。少しでも障害者のことを知ろうと、障害を持つ当事者はもちろん、障害者を育てる保護者や、障害者を雇用する経営者、障害者スポーツ団体を運営する人200人以上に会いに行くうち、彼らの悩みにアイデアで貢献できるという発見を得た。現在は「ゆるスポーツ」をはじめ、福祉とスポーツと広告をかけ合わせた企画をつくる仕事をメインの仕事としている。
「ゆるスポーツ」には、5つの要件があるという。
- 老・弱・男・女・健・障」誰でも参加できる。
- 勝ったら嬉しい。負けても楽しい。
- プレイヤーも観客も笑える。
- 第一印象がキャッチー。
- 何らかの社会的課題の解決につながっている。
(書籍『ガチガチの世界をゆるめる』より引用)
「たとえば、『500歩サッカー』というスポーツがあります。これは歩数が測れるデバイスを腰に装着して、500歩を歩き切るとゲージがゼロになり退場となるスポーツ。ただし3秒以上立ち止まると、センサーが認識して1秒に1ゲージ回復していくルールを入れているのがポイントです。そうすると、『お前、あと100歩だぞ!』と声を掛け合うようになるんです。声をかけられた方は、『ありがとう』と言って立ち止まります」

「ゆるスポーツ」は、単なる新しいスポーツの発明ではない。誰かのマイノリティ性を多くの人に伝える仕組みになっているのだ。
「実は500歩サッカーは、心臓病の友人と一緒につくったスポーツなんです。彼は少しは走れるけど、走った後に心拍を安定させるため休まなければいけない。でも、こまめに休んでいいスポーツってないですよね。だったら、みんなで休まないとできないスポーツをつくろうと考えました。試合が終わった後に必ずメッセージを言うんです。『皆さんが今やった楽しいスポーツは、心臓に何らかの病気を抱えている方の疑似体験でした』と。そうすると、教科書や記事で心疾患について知るよりも、身体知として身について、深く楽しく理解できるし忘れません。スポーツというのは、大量の情報を内包できて、それをひとに届けることができるメディアなんです」


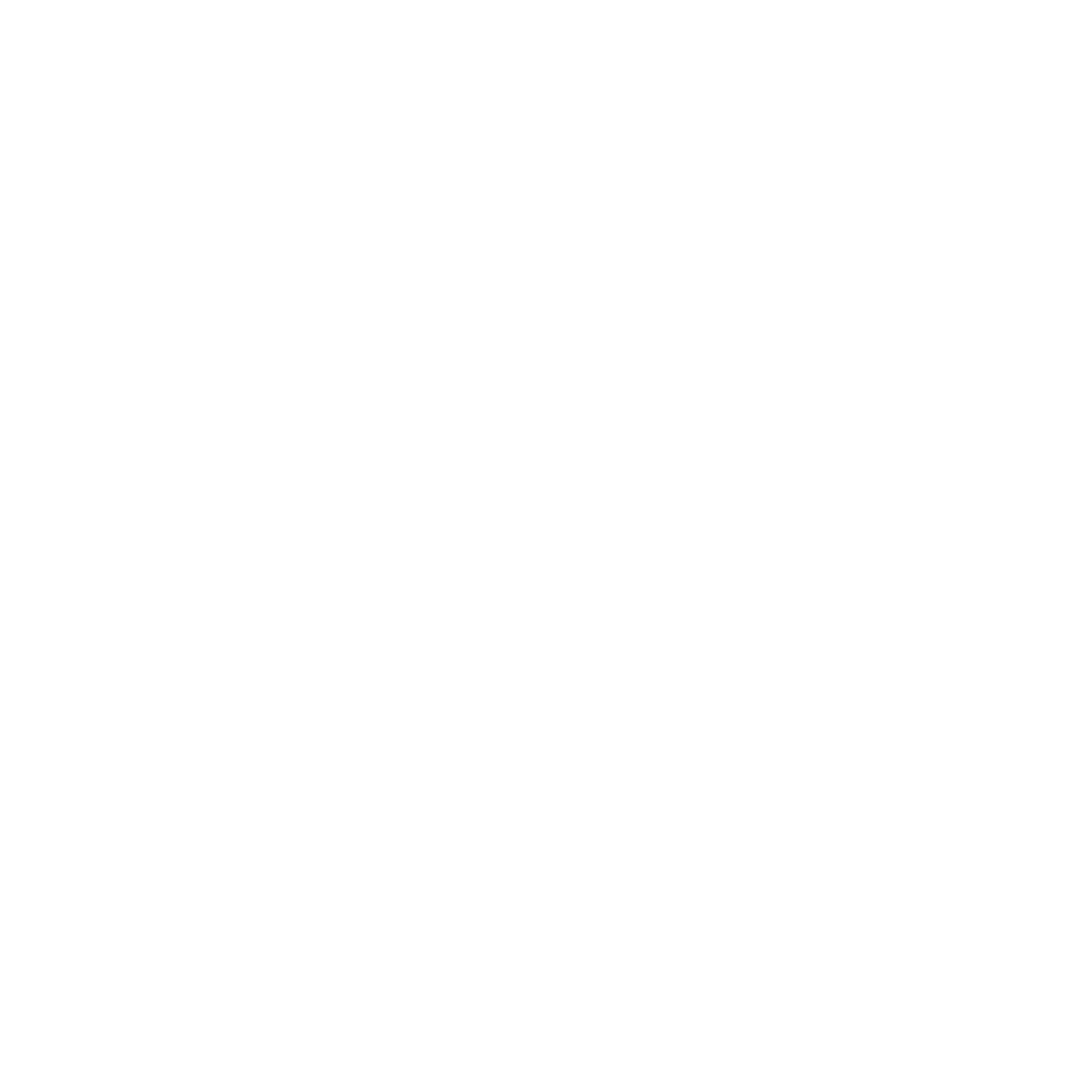

 メルマガ登録
メルマガ登録