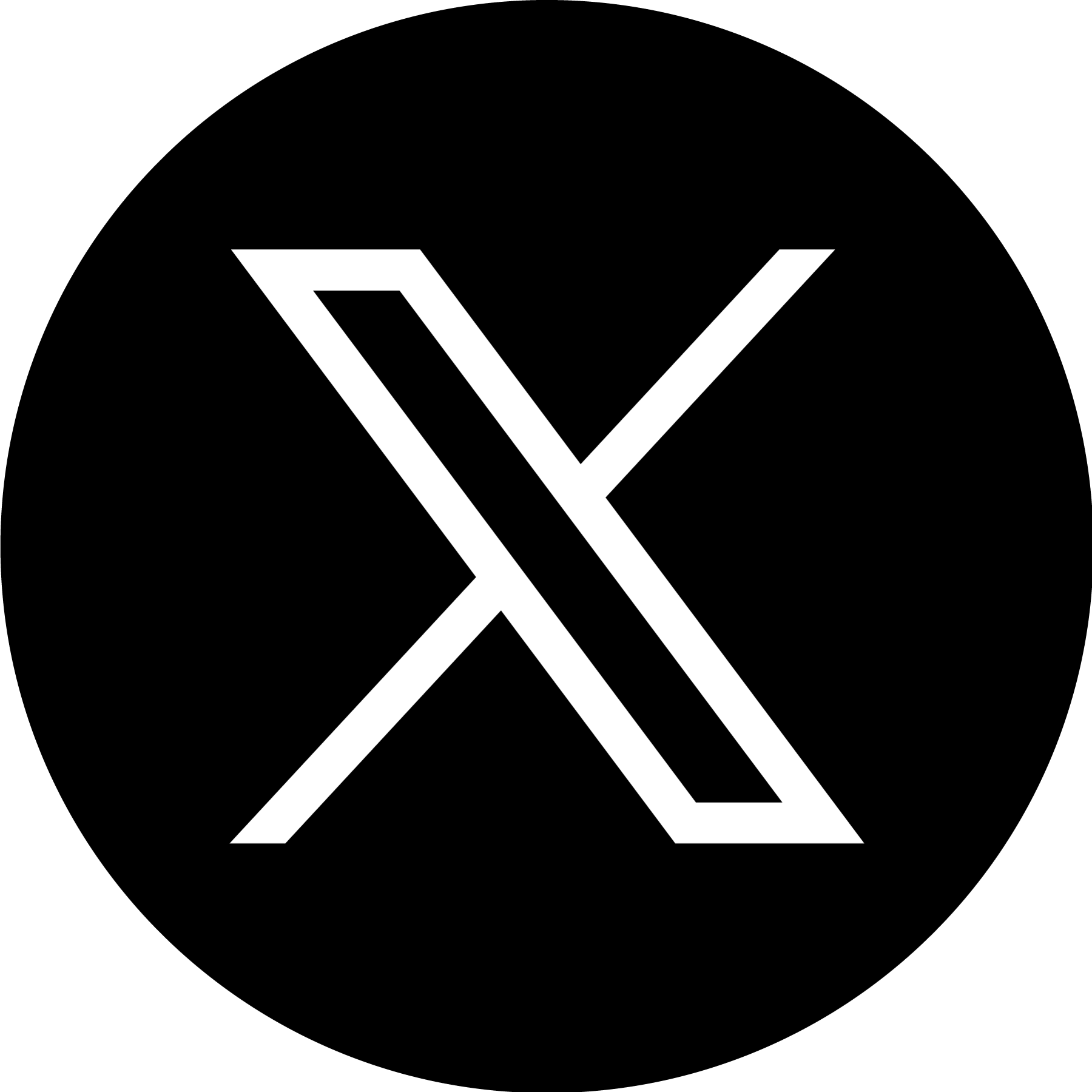マーケティングは、どこまで人間を理解できるのか #20
マーケティングは、あらゆる事象に生じる「消費者の感情」を軽視してはいけない
2023/06/30
感情は、消費者が経験するすべての事象に常に伴っている
先ほどのループのなかで、今回特に強調したいのは、外受容感覚と内受容感覚の処理は両方とも常に起こっているという点です。つまり、視覚や聴覚、嗅覚など五感を通して知覚が形成される過程では、それとともに付随する身体状態の変化が常に生じていて、内受容感覚が形成されているのです。さらに、それらが並行して生じているだけでなく、ある特定の脳部位(脚注2)がそれらを統合するような役割を持つという証拠も集まってきています(文献1,2)。
前回の記事で述べた通り、内受容感覚を通して処理される情報が感情の本質だと考えられています(文献3)。その内受容感覚が常に外受容感覚と統合されているなら、消費者が日ごろ経験しているすべての事象に、感情が常に随伴しているとも考えられます。生きて活動している限り、どんな状態、どんな刺激に対しても、ほんの微細な(気づきもしない)レベルから人生を揺さぶられるようなレベルまで、連続的に変化しながら、常に感情が生じているのです。
この仮説によれば、感情は、知覚や認知あるいは運動などの他の機能と区別することができず、それらに常に付随して、オーバーラップしているというのです。そして、内受容感覚、外受容感覚をあわせて総合的に予測誤差の和を最小化するように知覚や意思決定・行動が決まると主張されています。
このように感情とその他の機能が切り離せないというならば、実務の視点で関連が深いと思うのは、例えば「機能訴求と情緒訴求はどちららが効果的か」や「どのようにバランスをとるべきか」という議論です。統合的な予測符号化の枠組みによれば、そのような問いや区別自体がナンセンスかもしれません。機能的な訴求をしていたとしても、それを受け取った消費者の側では、それに付随した内受容感覚の変化、そしてそれに伴う感情(affect)が生じるのです。そして、その機能訴求の知覚・認知も、さらには、その先の意思決定や行動も、その感情を軸に形作られていくものとされます。
これは、情緒的価値に重みのあるカテゴリーに限ったことではありません。機能的な商材やカテゴリーにおける機能訴求だとしても、いかに事実を伝え理解してもらうかというよりは、そこからどのような内受容感覚・感情の変化がもたらされるかに重きを置くべきではないでしょうか。
また、タッチポイントや、マーケティングやブランディングのステージなどにもよりません。商品開発のデザインやコンセプトから、広告コミュニケーション、Web、店頭などあらゆる場面で考慮しておくべきだと考えます。

調査手法の観点からみると、このような考え方は、たとえば私自身も長らく関わってきた脳波を用いた効果測定とも整合性があります。そこでは、カテゴリーやマーケットに関わらず、また調査対象の素材にもよらず、基本的にある種の感情に関わる信号を中心として標準化した指標を使っていました。
このアプローチは、金融カテゴリーや耐久財、あるいは、機能訴求に頼ってきた一部の消費財メーカーなどのクライアントさんから懸念を示されることも多いのですが、市場レベルのデータとの相関を見ると、理解度や説得度といった指標よりも相関が高かったという経験を何度もしてきました。
とはいえ、この感情指標を中心にした調査は10年以上続いていることですし、感情訴求の重要性の指摘も大して新しいことではありません。では、ここでややこしい話をしてまで、もう一度引っ張り出している意味は、どこにあるのでしょうか。
それは、背景にあるメカニズムの理解に基づくことで、消費者へより効果的なアプローチの示唆が得られる可能性にあると考えます。具体的に見ていきましょう。


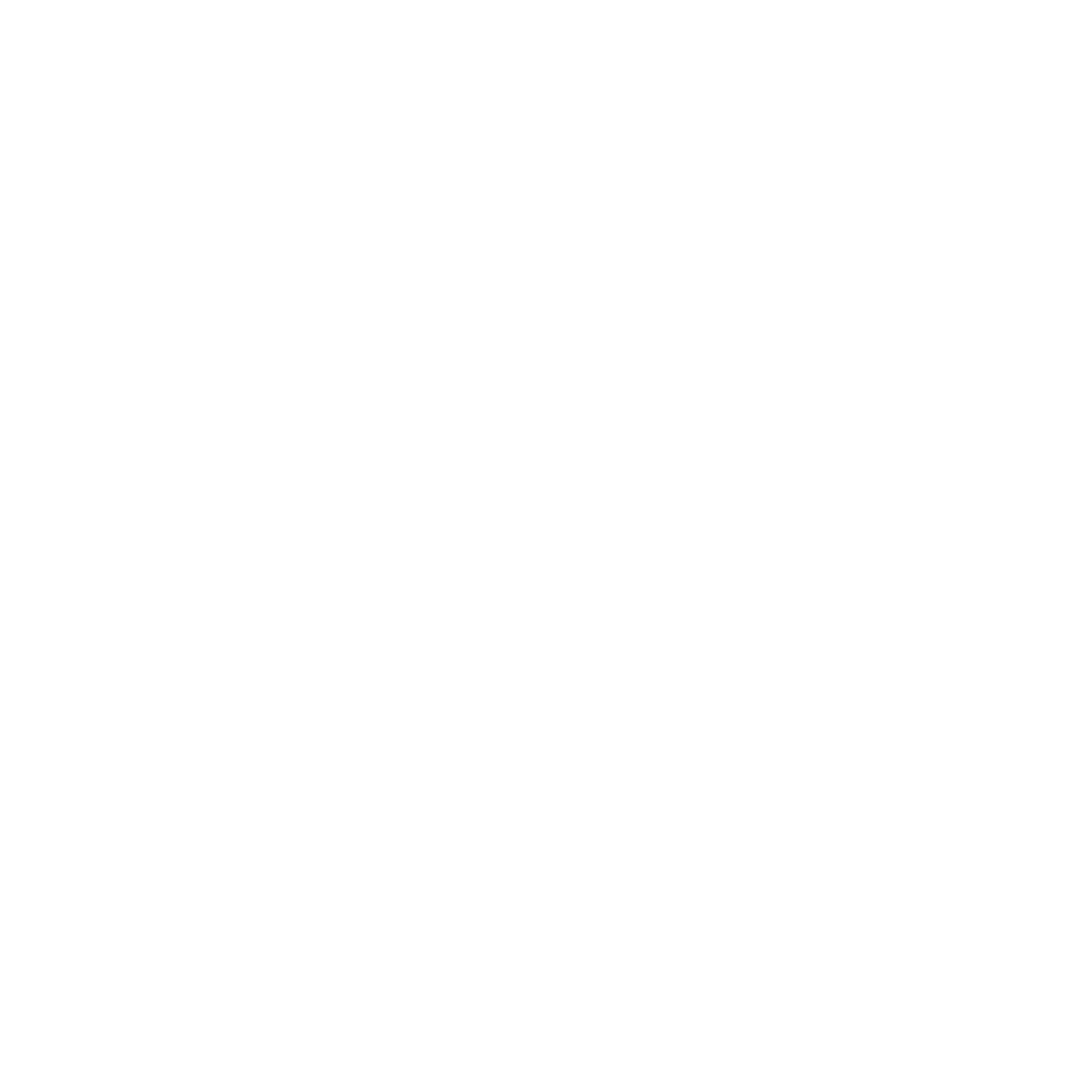

 メルマガ登録
メルマガ登録