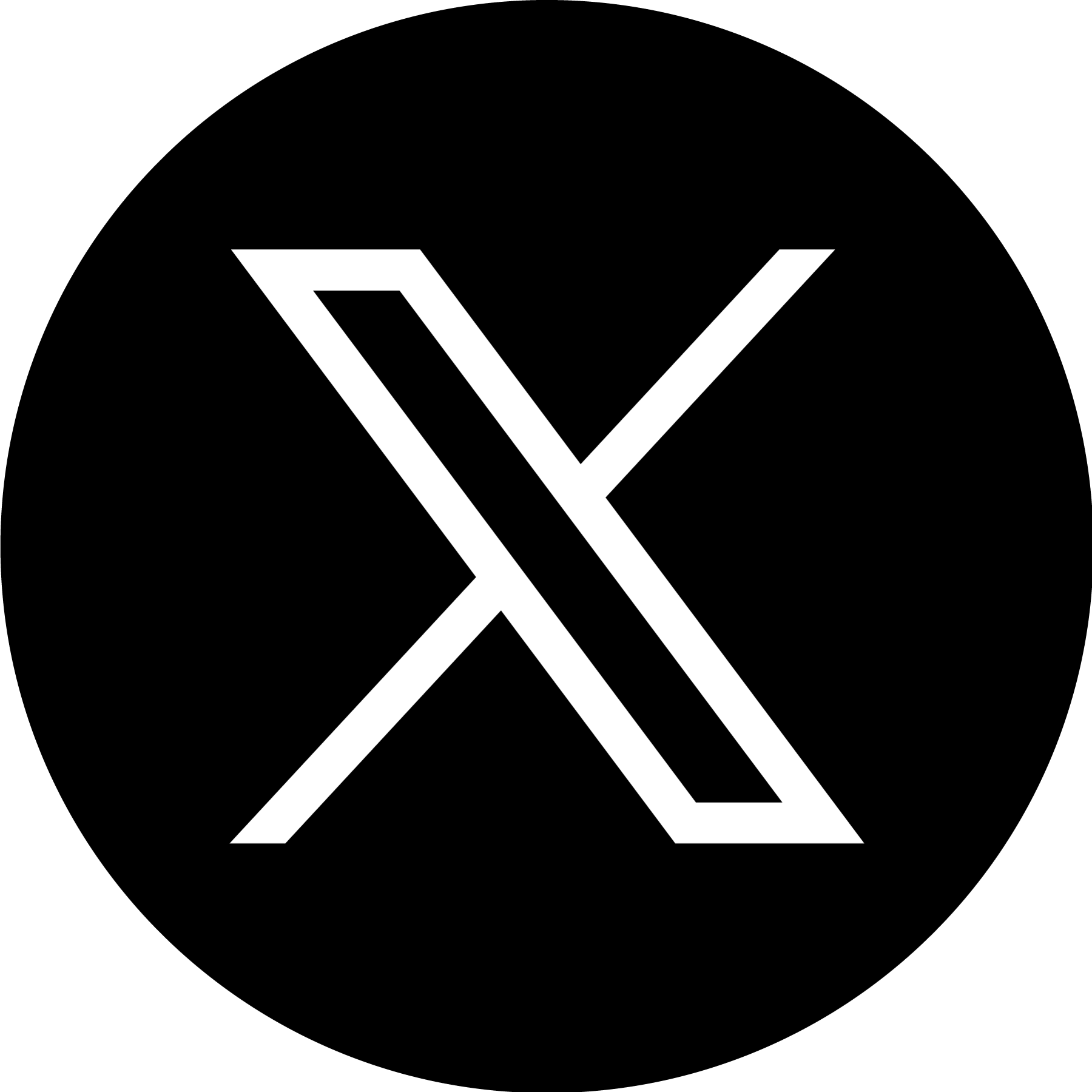古川裕也が見たカンヌライオンズ
【特別寄稿:古川裕也】今年。カンヌライオンズは、何を捨てて何を取り戻そうとしたのか。
90歳が言い当てたクリエーティビティの本質
ジャック・セゲラを見た。
最終日。ファイナル・セレモニーの中盤。恒例のThe Prestigious Lion of St.Mark Lifetime Achievement Awardの発表があった。毎年ひとりだけ選ばれる殿堂入り。1回目がジョン・ハガティ。2回目はダン・ワイデンが受賞している。毎年、カンヌのCOO フィリップ・トーマスが受賞者の業績を紹介した後、本人が現れてスタンディング・オベーションという流れで、クリエーティブを創ってきた受賞者へのリスペクトを示すという、ちょっといい時間が流れる。当然、全員スタンディング・オベーション。
けれど、今年はまったく違う時間になった。ヨーロッパ最年長のクリエーティブ・ディレクイター、ジャック・セゲラは、フィリップが自分を褒めたたえるスピーチを読んでいる途中、待ちきれないように踊りながらステージに出てきてしまったのだ。フィリップの静止も聞かず。ステージ中央で踊りながら叫び続けた。
「Love Idea」「Love Creativity」「Love Life」と。
噂には聞いていたが、ずいぶん色気のある、ありていに言えばクレイジーな90歳だ。
行儀のよくなったアドバタイジング・インダストリーとカンヌライオンズに、何が足りないかを見せつけるかのように。彼が僕たちにプレゼンしたのは「魅力的なヤバさ」。ヒトを動かす力のあるクリエーティブが必ず持っている、説明不可能な何かだった。
HumourとHumanity
2024のカテゴリー・メイキングでいちばん特徴的だったのは、30あるうち13のカテゴリーで「Use of Humour」というサブ・カテゴリーが設けられたことだ。カンヌの公式サイトに、「We ‘ve brought Humour to Cannes Lions」というタイトルのメッセージを掲載したことがみんなを驚かせた。さらに、ブランド・コミュニケーションにおける「Art of Humour」を称えるべしというメッセージが続く。
ここ10年以上、多くのクリエーティブパーソンからの「最近のカンヌあんまりおもしろくない」「正しいけどグッとこない」「華がない」などの声にやや過剰に反応したものだろう。本来、Humourとは、方法あるいは体質であって、カテゴリー化するものではないのだけれど。
今年は、Humanityを称揚する言説も多く聞かれた。HumourとHumanityは、「hum」という共通のラテン語を持っている。「土・大地」という意味の接頭辞で、人類が生きていく上での基礎となるもの。さらには、人間にとって欠くことのできない本質的な、なにやら体温を感じるものという共通項があったと推測できる。HumanityとHumourは、およそ人間のありようの根源をなすものだと、おおむかし、認識されていたと思われる。
当然A.I.との対比でそのあたりは語られているのだけれど、そもそもクリエーティブの仕事にとって何がいちばん大切なんだっけ、という問いを参加者全員が潜在的に抱えていた。これが今年の重要な特徴のひとつだと思う。
「Sammakorn/Sammakorn Not Sanpakorn」
人間がそもそも持っている喜劇性をアイデアにしたタイの不動産会社のCM。社名が日本でいう財務省と音が似ていることから起きるコメディ。タイのCMはヨーロッパ、米国にはないシュールで、プリミティブで、感情剥き出しなフィルムだけれど、アイデアはロジカルで人類共通のサイコロジーから構築されている。それゆえ、世界中の人たちが反応できる作品が生まれる。人間共通の特質を徹底的に描くと、必然的に喜劇が生まれるという表現原理の証明でもある。
けれど、Humourは実はとても難しい。なぜなら、明らかに国境があるから。世界共通の心理と論理を備えたアイデアでなければ、ライオンをとることはできない。
「Specsavers/The Misheard Version」
受診者が極端に少ない聴覚検査を受けるように促すキャンペーン。ロンドン中に、大ヒット曲の歌詞の聞き間違いを起こさせるというアイデア。1987年のヒット曲、Rick Astley 「Never Gonna Give You Up」の聞き間違いヴァージョンを本人が録音。You Wouldn’t Catch Thisを、Catch Nits(シラミ)と歌ったり。他愛ないのだけれど、みんな聞き間違い、言い間違いは大好き。狙い通り、SNS上でヒットして検査を受ける人が大幅に増加した。
「聴覚検査を受けましょう」というお題は、啓蒙したり、脅したり、よく聞こえることの楽しさを伝えたり。ほっておくと、殺風景なことになりかねない。こういう時、確かにHumourは有効だ。まず、感情が動くから。プラトンが「何かを学習する時、人はむしろ感情的である」と言っている。これがHumourの力であり、表現の力だ。それによって、みんなの知覚が開き、メッセージが豊饒に伝わるのだ。
Humourを生み出すには、というかすべてのコミュニケーション行為は、120%俯瞰的、客観的態度でなければならない。世阿弥が『花鏡』 のなかで唱えた「離見の見」である。それが受け手に届くと100%主観的にカラダとキモチが喜ぶのだ。
カンヌにHumourを持ち込むのだというメッセージを読みながら、2013年、チタニウムの審査を思い出していた。席が5日間ずっと固定で、僕は審査委員長 ダン・ワイデンの左隣だった。小さな声でゆっくり話す米国人らしからぬ人で、敬愛するユングの話、映画を撮ろうとしている長男の話、僕から見ればずいぶん華やかな昔話など、とても貴重な時間だったのだけれど、その上品な語りの合間にときどき「カンヌには、もはや何の魅力もない。完全に変わってしまった」というつぶやきが差し込まれていた。それは、まさにカンヌからHumanityとHumourが失われてしまったことに対してだった。アートとして痩せていくことを危惧していたのだ。
あれから10年。どこまで行っても、考え、創るのは人間でしかない、というクリエイティブ・パーソンにとって根源的な事実の確認が、生成A.I.登場によって逆に可能になったということだろう。
それは同時に「人間とは何か」という健全で意味のある問いが立てられたことでもある。この大きな問いは、これからも厳然と僕たちの前に存在し続けるだろう。


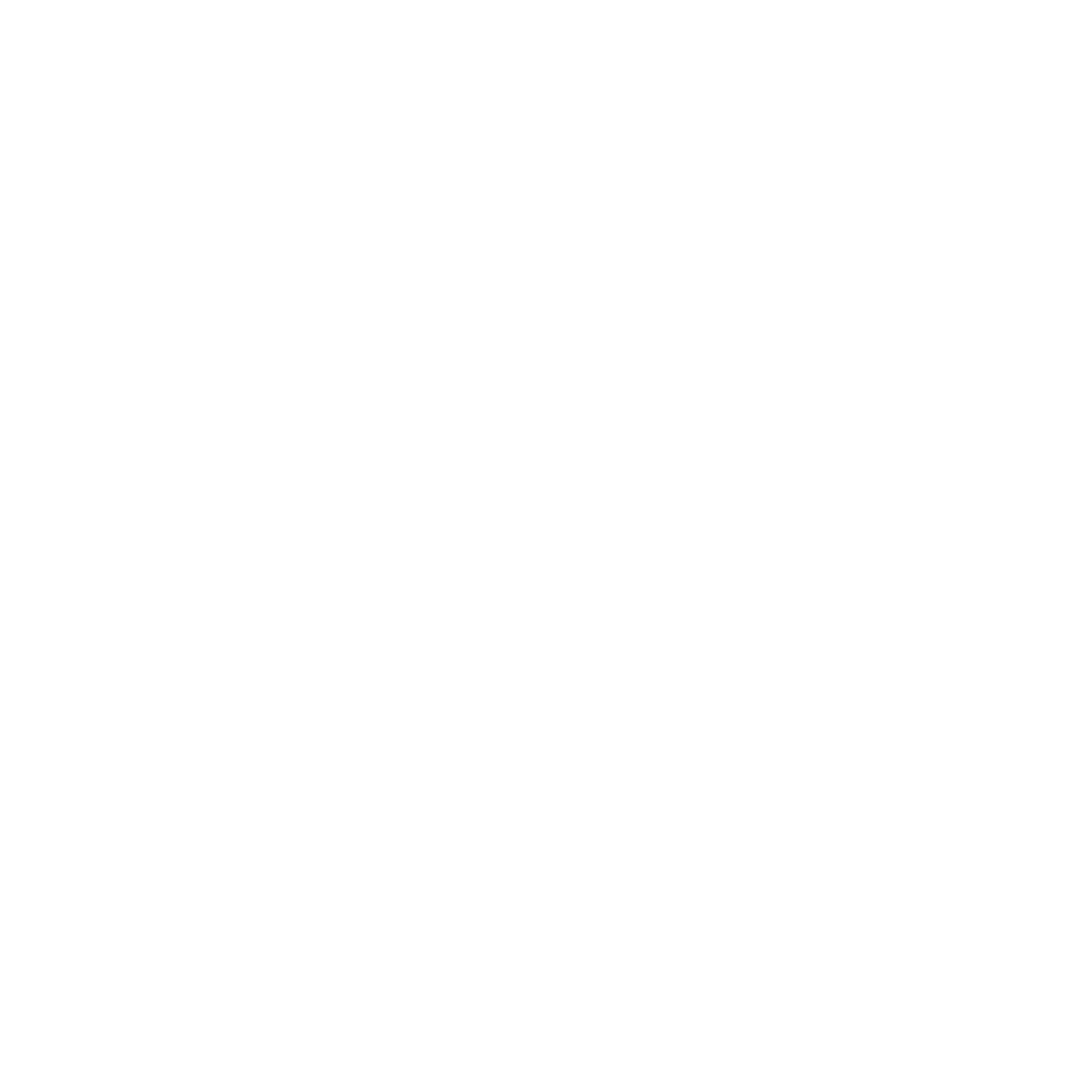

 メルマガ登録
メルマガ登録