いよいよ本戦! 意識していたのは「陽キャ」と「ギャル」
そして、いよいよヤングカンヌ本戦。カンヌライオンズ初日である月曜日にPR・メディア・フィルム部門、火曜日にデザイン・デジタル・プリント部門の課題発表が行われます。フィルム部門は課題発表後48時間、他部門は課題発表後24時間で企画づくりとアウトプット(プレゼンシート等)を提出するというスケジュールです。
課題発表の際には、実在するNPO・NGOなどのメンバーが登壇し、課題のアナウンスのほか、取り扱うテーマに関しても様々な情報が提供されます。
デジタル部門の課題は、生物多様性。「BEE:WILD(野生ハチの保護団体)」をクライアントとし、「How can Gen Z make wild bees famous?(Z世代は、どのように野生のハチを有名にできるか?)」という課題に対してデジタルキャンペーンの企画・提案が呼びかけられました。
BEE:WILDのメンバーは、野生のハチの受粉が食物をはじめとする自然のエコシステムに大きく貢献していることや、過去に取り組んだキャンペーンの実例などを紹介。課題発表後の質疑応答では、各国代表から質問が飛び交いました。質問者が多く、セッション終了後にクライアントの前に長蛇の列ができた部門もあったそうです。
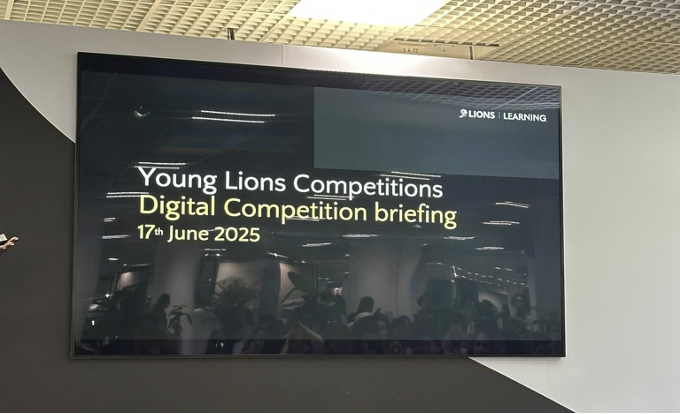
デジタル部門のブリーフィング(課題発表)
デジタル部門のアイデアを練るうえでまず重要になるのは、どのようなプラットフォームやメディアを選ぶのか?という部分。なんといってもデジタル部門は最も参加人数が多いカテゴリーであり、全参加者の約4人に1人がデジタル部門参加者なのです。一方、全世界にユーザーがいるサービス(ヤングカンヌで活用しやすい媒体)は限られているため、アイデアが被りやすいという特徴があります。実際に「Bee」に発音をかけやすかった「Airbnb」は片手分ぐらいのチームが提案していました。
また、ヤングカンヌ本戦の特徴の一つに、「インサイト」に関する評価が日本予選に比べて重いことが挙げられます。ユーザーの行動特性や感情を正確にとらえ、接着の強いアイデアにつなげられているかが重視される傾向があります。Z世代という直球なターゲットを目の前に、「自分たちって、いつも何考えているっけ…?」と不思議な思考をしつつ、アイデアのブレストと取捨選択をしていきました。

作業場所は、大学の食堂のような空間。初日にはヤングカンヌ限定グッズ、コンペ日にはランチボックスが配られます。
難しかったのは課題のゴール設定。予選課題はもちろん、数年前までのデジタル部門では「行動や購買を促す」「認知度を上げる」といった“KPI”的な指標が企画の目標として設定されていました。一方、今回の課題のゴールは「Z世代を“通じて”野生のハチをバズらせること」。特定の目標点というより「広がり」を重視したキャンペーンは、逆算でのアイデア出しが行いにくく、苦戦したポイントでした。ただ、現在のデジタルキャンペーンが置かれた環境を色濃く反映しており、ヤングコンペティションとしてはとても優れた課題設定だったと感じています。
一方、終始コンセプトに掲げていて正解だったなと思ったのは「ノリ」と「テンション」。東アジア勢は例年アイデアが真面目すぎる傾向にあると聞いていたこと、課題自体がZ世代ターゲットかつエッジの効いたアイデアを求められていたこともあり、どのような空気感の企画を出すかは開始1時間でチューニングを完了させていました。
意識していたのは「陽キャ」と「ギャル」。具体的に言うと、「脳内にKemioさん(日本在学中に若者の間で人気になり、現在はアメリカ在住のタレント)を宿す」がモットーでした。途中、アイデアに詰まったり時間が足りずバタバタした場面もありましたが、それらの焦燥をアウトプットに持ち込まずに済んだのは、最初にノリとテンションをしっかり決めておいたおかげでしたね。
人は焦るとつい「正解」を計算したくなってしまいますが、ここは遊び心も重要な大会。終盤は、「アウトプット自体のノリ」さらには「2人チームの1人としてのバランス(遊び心担当がどちらか)」を感覚的にチューニングしつつ、アイデア自体に破綻や遠回りがないかを左脳的に判別する、という頭の使い方をしていたように思います。

課題提出直後のデスク。時刻はもう夕方ですが、ここからやっとランチタイムでした。
本戦の結果は・・・南仏の晴れ空の下で噛み締めた悔しさ
最終的に私たちが提案したアイデアは「FLOWER PLAY BUTTON」。
Z世代に大きな影響力を持つYouTuberを起点に、金の盾・銀の盾(YouTubeの盾=PLAY BUTTON、一定のチャンネル登録者数を達成するとYouTubeから授与されるアイテム)に新たな「花の盾」を加えるというキャンペーンです。
社会に良い活動や発信を行うYouTuberを「Wild bee」に見立ててアイコニックに表彰し、定量的ではなく定性的な評価軸をつくることを目指しました。YouTubeでは「盾」をもらった時に「開封動画」をアップロードする行動が一般的です。すでに注目を集めているこれらのフォーマットを活用してメッセージを広げていく、という戦略に基づいています。

「FLOWER PLAY BUTTON」提出スライド
結果発表は、カンヌライオンズ最終日の金曜日朝に行われます。屋外ステージに全員が集まり、各部門のゴールド・シルバー・ブロンズ(1~3位)、ショートリスト(入賞)が次々と発表されていきます。
残念ながら、今年の日本勢の受賞はゼロ。南仏の晴れ空の下で悔しさを噛み締め合ったのは、えもいわれぬ瞬間でした。

結果発表後の表彰式。皆、国旗などのアイテムを持ってきており、改めて各国代表なのだと実感しました。
ちなみに、デジタル部門で優勝したのは、「Tinder(マッチングアプリ)」に“3人目”のマッチング相手を表示する「THE WILDEST PROFILE」という企画。
表彰式後に優勝ペアに話を聞きに行ったのですが、あまりにも型破りな発想と国際大会でこれを提案する度胸に肝を抜かれたのを覚えています。ですが、冷静に分析してみると、シンプルなインサイト・パワフルなアイデアと、与えられた課題に対してしっかり芯の通った解を出していました。
これは普段の仕事にも言えることですが、「ひとことで伝わるアイデア」が持つパワーはとても大きいです。共感しやすく、人にも伝えやすい、シンプルでインパクトのあるコンセプトは、広がりという意味では精密な戦略やプランニングにも勝ると改めて感じました。
(後編に続く)

- 1
- 2




 メルマガ登録
メルマガ登録

