リテール・EC
生活者目線を軸に、安心安全なリテールメディアの発展を願い、ガイドライン作成【リテールメディアコンソーシアム座談会】
2025/10/28
小売やメーカー企業などでつくる「リテールメディアコンソーシアム」がリテールメディアに関するガイドライン(指針)を作成した。
リテールメディアコンソーシアムは、リテールメディアのあり方を規定し、新たな基準を設定するプラットフォームとして機能する団体。
作成に携わったTMI総合法律事務所 パートナー弁護士の寺門峻佑氏、電通 チーフ・リサーチ・ディレクターの朱喜哲氏、フェズ データ基盤部 部長の福田大賀氏が座談会を実施。後編では、ガイドラインの運用を通して、目指しているリテールメディアのあり方などについて語った。
前編:リテールメディアの信頼性向上のためガイドライン作成。その内容と意図は?【リテールメディアコンソーシアム座談会】
リテールメディアコンソーシアムは、リテールメディアのあり方を規定し、新たな基準を設定するプラットフォームとして機能する団体。
作成に携わったTMI総合法律事務所 パートナー弁護士の寺門峻佑氏、電通 チーフ・リサーチ・ディレクターの朱喜哲氏、フェズ データ基盤部 部長の福田大賀氏が座談会を実施。後編では、ガイドラインの運用を通して、目指しているリテールメディアのあり方などについて語った。
前編:リテールメディアの信頼性向上のためガイドライン作成。その内容と意図は?【リテールメディアコンソーシアム座談会】
ガイドラインは、より安全に、より遠くまでドライブするための「ガードレール」
ーーガイドラインの中で、特に重要なポイントとなる部分を教えてください。
福田 フェズは、ドラッグストアやスーパーマーケット、ホームセンターなど複数の小売企業からデータをお預かりして、横断的に分析や活用ができるソリューションを提供しています。リテールメディア活用が進む中で、小売横断でのデータ活用ニーズも高まってきているので、どのようなデータの種類や利用の方法があるかが書かれている点はポイントだと思っています。
また、この領域を牽引する企業の開発チームとして、データが各企業の事業部でどのように使われるか理解をより深めるために、このガイドラインを教科書的に使っていきたいですね。私はクライアントと対外的な調整を行うこともあるのですが、他のメンバーが同じように調整に携わる場合に、この法的観点で大丈夫かというチェックリストとしても使えると思っています。
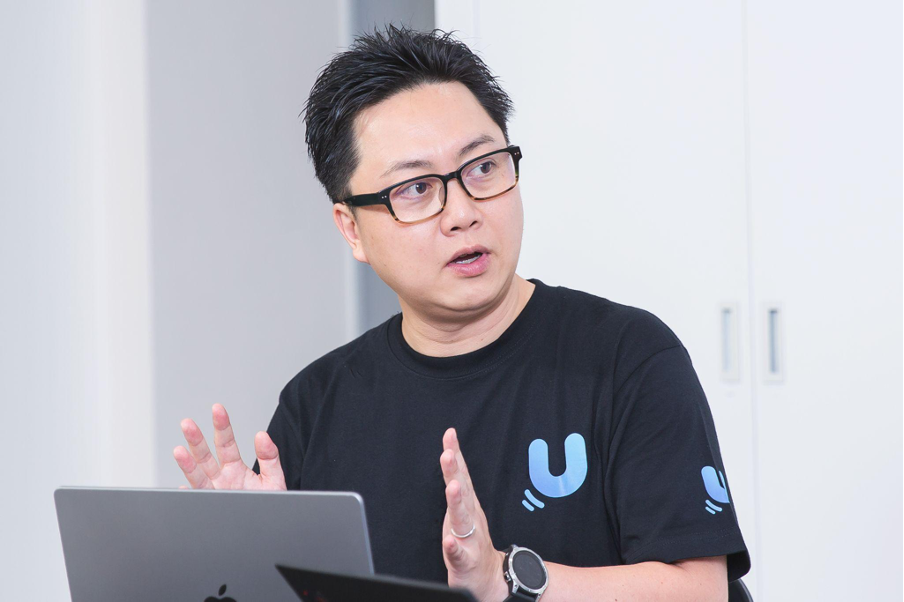
株式会社 フェズ
開発本部
データ基盤部
部長
福田 大賀氏
自治体向け基幹システム開発を経て2017年にフェズ入社。
以来、データ基盤の立ち上げや小売企業とのデータ連携を推進し、現在はリテールメディア領域を支えるデータ基盤の設計・開発・運用を統括。
技術とビジネスをつなぐ役割として、データ利活用による新たな価値創出に取り組んでいる。
開発本部
データ基盤部
部長
福田 大賀氏
自治体向け基幹システム開発を経て2017年にフェズ入社。
以来、データ基盤の立ち上げや小売企業とのデータ連携を推進し、現在はリテールメディア領域を支えるデータ基盤の設計・開発・運用を統括。
技術とビジネスをつなぐ役割として、データ利活用による新たな価値創出に取り組んでいる。
朱 まさにこのガイドラインは、使い方が大事だと思っています。法律が分っている法務部門の人と、技術が分っている事業部の人が会話をするときに、双方が参照できるものだと考えています。「どのようなポイントに相談するべきことがあるのだろう」「ここは外部の専門家に相談した方がいいな」などと考えるための入り口になると思っています。
法律さえ守っていれば炎上しないかといえばそうではありません。現行の法律上は問題がなくても、社会的なリスクはゼロになりません。どのような理念を掲げるか、どのような指針で扱うのかという倫理的な部分が大事であることを、このガイドラインを作成しながら実感しました。このガイドラインは、事業部がアクセルを踏んで法務部がブレーキを踏むのではなく、事業部がより安全に、より遠くまでドライブできるようにするための「ガードレール」のような役割を果たすと考えています。
特に5章の「生活者の視点から見たリテールメディアのあり方」というセクションが、このガイドラインのユニークな点だと思います。最初に「データを『預かっているもの』として扱う」という姿勢を表明していますが、これは法律的な定義というよりも、思想に近いわけです。データの主体はあくまでも消費者自身なので、我々はそれを信託されて扱っているのだ、と。このスタンスが、このガイドラインの思想的な中心点なので、初めに確認してほしいポイントですね。その上で、テクニカルな法解釈の部分が出てくるという見方をしてもらえればいいのではないかと思います。
寺門 私もまさに5章が一番重要なポイントだと思います。おそらく小売さんの置かれている立場やリテールメディアを活用する目的、法律への対応の仕方などは、各社それぞれ異なりますし、ケースバイケースだと思うのですが、どの場合も共通して頭の中に置いて取り組んでもらいたいのが5章の考え方です。このポイントを理解していないと、そもそもどこにリスクがあって、何に配慮してビジネスを組み立てたらいいのかが分からないと思います。
データは消費者のものだということを前提として、安心と便利さを両立する。それを考える上では、やはり法律のポイントを押さえることが重要だという構造です。法律のポイントを具体的に解説している部分もありますので、そこもざっと見てもらいながら、実務に生かしてもらえればと思います。
ガイドラインを、今後もより進化・浸透させていきたい
ーーガイドラインの運用やワーキンググループの活動について、今後の展望をお聞かせください。
福田 今回のガイドラインはあくまでも分かりやすく記載していますが、今後はもう少し抽象度を上げたものもつくりたいと思っています。また一方で、より具体的な、事例に近いものももっと打ち出していくことで、より実務に生かすイメージが湧きやすくなるのではという意見も出ています。抽象度を上げることと、具体を深めていくことの両方に取り組んでいきたいと思っています。
朱 そうですね。こうしたガイドラインは、つくって終わりにしないことが一番大事だと思っています。ここに書かれていることが本当に実行されているのか、これが本当に実効性を持つのかが非常に重要なポイントですし、いま大きく注目されているリテールメディアという新しいメディア、新しい業態が、広い意味で市民社会から信頼を得られるかどうかにも関わってきます。そこは競争ではなく協調の領域として、まだまだリテールメディアに関わる多様な関係者で力を合わせて、一つの業態を健全に発達させる段階にあると思っています。
今後、新しいタイプの購買データによってさらにいろいろなことが実現できるようになっていきます。それに伴って、現時点では予測できていない使い方やリスクも生まれ得るでしょう。だからこそ、今回は理念的な部分に踏み込んでいるので、この観点から自分たちの技術を吟味したり、仕様を検討したりするということに役立ててもらえれば。まだ具体的な構想はありませんが、たとえば一定の基準をクリアしたメディアを認証するといったこともあり得るかもしれません。そうした方法も視野に、市民社会と正しく関係を築きながら、リテールメディアという新しいメディア、新しい業態を伸ばしていきたいと考えています。
寺門 言うまでもありませんが、このガイドラインは、リテールメディア事業の足かせにするつもりで作成したわけではありません。むしろもっと広めていくために、データを安全に活用していると消費者に胸を張って言える体制をつくることが必要だと考えて策定しました。
いったんはベースラインのつもりで作成しましたが、今後リテールメディアがどのように発展していくのか、そしてどのように広めていくのかという観点で事業部の方々からフィードバックをいただきながら、より安心してリテールメディアのビジネスに取り組んでいける、対外的にも何を守ってやっているのかをしっかりと説明できる指針にしていければと思っています。

TMI総合法律事務所
パートナー弁護士
寺門 峻佑氏
TMI総合法律事務所パートナー TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社取締役。日本国・ニューヨーク州弁護士、情報処理安全確保支援士。内閣サイバーセキュリティセンタータスクフォース、滋賀大学データサイエンス学部インダストリアルアドバイザー、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)技術委員などを歴任。国内外のデータ保護法対応・セキュリティインシデント対応、プラットフォーム開発・ライセンスビジネス等のIT・海外展開に関する法務、IT関連の国内外紛争・不正調査案件を主に取り扱う。
パートナー弁護士
寺門 峻佑氏
TMI総合法律事務所パートナー TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社取締役。日本国・ニューヨーク州弁護士、情報処理安全確保支援士。内閣サイバーセキュリティセンタータスクフォース、滋賀大学データサイエンス学部インダストリアルアドバイザー、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)技術委員などを歴任。国内外のデータ保護法対応・セキュリティインシデント対応、プラットフォーム開発・ライセンスビジネス等のIT・海外展開に関する法務、IT関連の国内外紛争・不正調査案件を主に取り扱う。
福田 リテールメディアにいろいろな企業が取り組んでいる中で、グレーなデータの使い方になってしまっている事業者が一定数いるのはすごくもったいないです。ガイドラインで示したような基準が浸透していけば、もっといいやり方が確立できると思うので、グレーなものを排除していくのではなく、グレーなものをあるべき形・消費者にメリットのある形にしていくという思いを、今後も大事な芯として持っていきたいと思っています。
寺門 そうですね。そもそもリテールメディアは、消費者にとってもメリットのあることをやっているわけですから、みんなWin-Winになれるはずなんです。そのメリットとともに、法律やプライバシーの観点からこんなふうにデータを扱っていますということを明確に示せば、消費者の皆さんは賛同してくれると思います。
ゆくゆくは、このガイドラインがリテールメディアを扱っている方に標準的に活用されるものになっていけばいいと思っていますし、そうなるためにそぐわない部分があるのであればチューニングしていきます。福田さんが言うように、より抽象的なもの、より具体的なものにも取り組んで、より一層役立つものにしていきたいですね。
朱 冒頭の寺門先生のお話にもありましたが、事業部が攻めて法務部が守るという姿勢で分業的になると、二重にコストがかかるわけですよね。でも、最初のプロダクト設計の時点からこのガイドラインを参照しながら一緒に進めていければ、スピーディーですし、コミュニケーションコストも削減できます。そんなふうに使ってもらえるようにこのガイドラインを浸透させていくことが、これからの課題かなと思います。




 メルマガ登録
メルマガ登録
























