AIエージェントと働くのが当たり前の時代がやってくる
加茂 今回、Xplorersのセッションに登壇いただく三井住友フィナンシャルグループをはじめ、AI活用の先進企業が取り組んでいるのが、「AIエージェントと働くのが当たり前」というカルチャーをつくることです。
AIエージェントを上手く使いこなし、仕事の効率を高めていこうとする際には、先ほど馬渕さんがおっしゃった組織の再設計だけでなく、“AIと共創するカルチャー”も醸成する必要があると感じています。
そしてそのカルチャーは、今までのデジタルカルチャーとは異なる、何か新しいものであるような気がするのです。アメリカでは、AIに対して「侵略される」という恐れのイメージが強く、反対運動も活発です。一方、昔から「鉄腕アトム」が好きな日本人は、AIと非常に上手くやっていけそうなイメージを持つのですが、いかがでしょうか?
馬渕 確かにそうですね。とはいえ、iPhoneが登場した当時、日本ではしばらく「自分はガラケーを使い続ける!」と宣言する“ガラケーおじさん”が存在し続けていたことも事実です。日本人って、大きな変化が起こった時に一瞬引いてしまうところがあるんですよね。そして、しばらくすると何事もなかったかのように使い始める(笑)。AIに対しても同じ反応で、今は何となく引いている状況なのかなと思います。
面白いのが、今年に入ってから20-30代女性の利用率が顕著に伸びていると言うことです。人生相談や占いなど、非常にパーソナルな相談ごとをするのに、ChatGPTを使う人が増えているのだとか。これまではAIにそれほど縁がなかった人が「便利!使える!」と感じ始めているようなのです。
これは、これからAIが一般化していく上でとても重要な変化だと思います。一般の人が「質問に答えてくれる存在」「寄り添ってくれる存在」と感じられるほど、AIの受け答えが自然でレベルの高いものになり、人間同士がコミュニケーションを取る感覚と擦りあってきている。それほどまでに、AIの性能が進化しているということです。誰もが当たり前のようにiPhoneを持つようになったように、AIが当たり前の存在になっていく、一つの兆しといえるかもしれません。

AIによって変わるマーケティングの常識
加茂 企業目線の話でいうと、最近、某大手スーパーマーケットのトップとお話ししたときに「AIエージェントが怖い」とおっしゃっていたんです。AIエージェントがどんどん賢くなり、色々なアドバイスをもらう中で、最近の提案が「現在の施策の延長線上」ではないものになってきていると。これまでは広告・プロモーションのやり方に関するアドバイスだったのが、極端にいえば「別の事業をやったほうがいい」と提案してくることもあるのだそうです。こうした中で、「マーケティングのあり方が今までとまったく変わってしまうのではないか」と恐れているとのことでした。
馬渕 今、AIO(AI Optimization:AI最適化)という言葉が出てきています。AIエージェントを前提として、企業側のエージェントをどうつくっていくかを考える必要があるんです。これまでは、人間が情報を検索した時、企業はWebサイトで受け止めていました。これからは、AIエージェントが情報を取りに来て、企業もAIエージェントで受け止める時代がくるといわれています。
お客様にいかに興味を持っていただくかを考えて、AIエージェントに渡す情報の種類や粒度を整理・管理することが重要になってきます。インターネットやスマートフォンがマーケティングに大きな変化をもたらしたように、AIもマーケティングを大きく変えていくと思います。
加茂 私たち一人ひとりのパーソナルなAIエージェントが生まれ、個人のことを深く理解した上で好みや状況に合わせた提案をしてくれる世界は、いち消費者の目線で見れば快適で、良いこと尽くしだと思います。しかし、企業の立場に立つと、この環境を追い風にできる企業と、チャレンジングな状況に置かれる企業とにはっきりと分かれそうですね。
馬渕 おっしゃる通りですね。AIによって、マーケティングそのものがなくなることはありませんが、やり方は大きく変わる。その前提に立たなければならないと思います。
これまでは「真ん中」の作業部分の負荷が大きく、目的に立ち返って全体戦略を見直したり、効果を見ながら施策の投資配分をチューニングしたりする余裕がなかった企業も多かったのではないでしょうか。AIが作業を担うようになるこれからの時代は、事業成長や市場創造のために必要なマーケティングを設計・評価・実行することに、人間の能力や労力を使っていくべきだと思います。
学校教育にも変化への対応が求められている
加茂 AIが当たり前の社会が到来する中、学校教育にも問題意識を持っています。たとえば調査・分析スキルの重要度が下がっていくことが明らかなのに、今までのように漢字ドリル・計算ドリルをやっているだけでいいの…?と。AIが当たり前の社会で求められることと、教育現場で行われていることのミスマッチが起こってきていると感じます。
先日、米テキサス州オースティンにある私立学校「Alpha School」の話を聞きました。同校では、数百人の生徒を対象にAIチューターを活用した個別最適化教育を提供しています。先生はあくまでナビゲーション役。子どもたちはAIエージェントと1日2-3時間勉強するだけで、楽しみながら能力を伸ばしているようです。個々の子どもの能力に合わせてカスタマイズした教育を行う有効性が実証され、今後全米に広げていく構想もあるようです。
このように学校教育もシフトしていかないと、社会の実態に追いつかないのではと危機感を持っているのですが、馬渕さんはどのようにご覧になりますか?
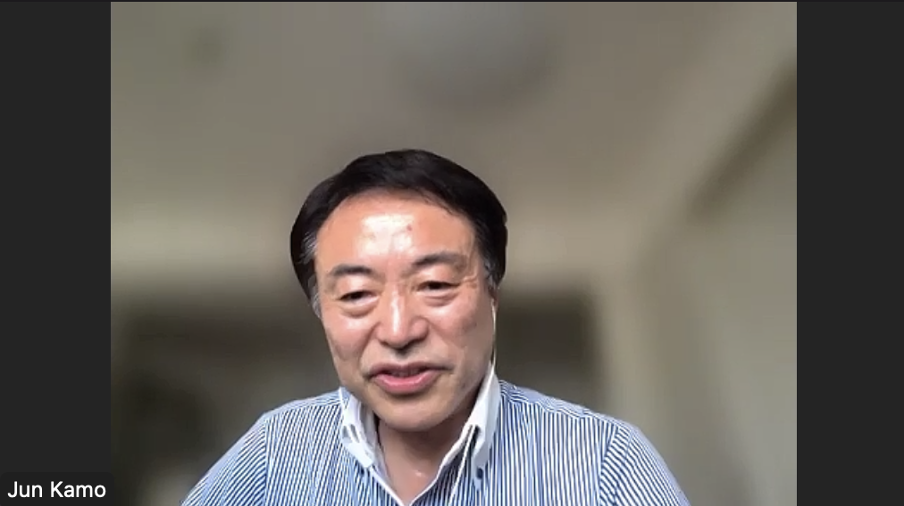
馬渕 教育は大事ですね。GoogleのAIモデル「Gemini 2.5 Pro」のIQは130くらいあるわけですから、もう「AIに教わる時代」がきていることは間違いありません。すべてのインターネットや書籍のデータを学習しており、圧倒的な知識量があるわけですから、知識教育についてはAIを活用しない手はありません。
一方、たとえば文化や哲学、コミュニケーションなど、知識以外の部分もきちんと教える必要があります。知識教育はAIを存分に活用し、それ以外の人間力を上げていく部分は、人間がしっかり教えていくべきでしょう。これまでの学校教育は、知識教育に押し出される形で、人間力を磨く部分に十分な時間を割けなかったという反省があると思います。AIの浸透を良いきっかけとして、教育の全体像を見直す動きも生まれるといいですね。
AIが前提の社会になっていくことは間違いありませんから、その中で良い社会をどうつくるかーー“AI for Good”について議論・構想していくことは、我々大人の役割ではないかと思います。Xplorersの場でも、そういう議論ができるといいなと思っています。
Xplorersで感じてほしい、日本有数の企業の経営トップの覚悟
加茂 インターネットやスマートフォンが登場して、ビジネスを取り巻く環境が大きく変わったように、AIの浸透・社会実装が急速に進む現在は、歴史の大きな転換点にあると認識しています。
これほどまでに大きな変化に対応し、さらに先手を打っていくためには、現場からのボトムアップだけではなく、経営トップが先頭に立って変革を宣言・推進していくことが求められます。
東日本旅客鉄道、ヤンマーマルシェ、三菱地所、三井住友フィナンシャルグループ、東芝、日清食品ホールディングス、花王、三井化学……Xplorersのセッションのスピーカーは、「トップが責任をもつ」という覚悟で変革を推進している経営・マネジメント層の方ばかりです。
Xplorersは、トップが自らの責任を持って会社全体を変革する動きを牽引されている方々の思考や取り組みを聞ける、他にない機会です。参加する前と後で、人生が変わるほどの経験ができると、自信を持っておすすめしたいと思います。
 Xplorers公式サイトは、こちら
Xplorers公式サイトは、こちら
Xplorers 開催概要
- 名称
- Xplorers(エクスプローラーズ)
- 日時
- 2025年8月26日(火) 10:00-20:30(9:30受付開始)予定
- 会場
- シェラトン都ホテル東京
〒108-8640 東京都港区白金台1丁目1-50 - 参加方法
- 事業変革や新規事業創発に関わる経営層・マネジメント層(審査あり):無料
同領域を支援するパートナー企業のエキスパート:250,000円(税込275,000円) - 定員
- 事業変革や新規事業創発に関わる経営層・マネジメント層(審査あり):100名限定
同領域を支援するパートナー企業のエキスパート:100名限定 - 主催
- 株式会社ナノベーション
- 特別協力
- dentsu Japan

- 1
- 2




 メルマガ登録
メルマガ登録

