構想と実行にギャップ
日本IBMは9月5日、IBM Institute for Business Value(IBV)が世界のCMO、および最高営業責任者(CSO。本記事では統一してCMOと表記)1800人を対象に実施した最新の調査「CMOスタディ2025『CMOが導く、AI時代の5つの成長策』」(※)の日本版を公開した。
それによると、CMOの54%(世界、日本とも同率)が「AI戦略を具体的成果に結びつけるための運用上の複雑さを過小評価していた」と回答し、自社組織が「意思決定と業務効率を向上させるために、エージェント型AIをプロセスに組み込む準備ができている」と答えた割合は2割に満たなかった(世界17%、日本19%)。
世界のCMOの81%は、AIを「既存のオペレーションを抜本的に再構成し、戦略の実行力を飛躍的に高めるゲームチェンジャー」だと認めている。一方で、「自社従業員がAIエージェントによってもたらされる文化とオペレーションの変化に対して十分に準備できている」と回答したCMOは世界23%、日本30%にとどまった。また、8割強(世界84%、日本88%)のCMOは「既存のオペレーションがあまりに硬直、分断しているために、AIテクノロジーを活用しきれずにいる」と回答した。
AIの戦略的重要性が広く認識されているにもかかわらず、CMOは自身の役割の変化に適応する中で「主に断片化されたシステムに起因する『構想と実行のギャップ』に直面している」(IBM)という現状が浮かび上がった。
※日本版全文はこちら。調査時期は2025年第一四半期
統合・連携強化で成長率に差
本調査からは、テクノロジーの進化に伴ってCMOの役割が拡張している実態もうかがえた。CMOの6割以上(世界67%、日本66%)は「生成AIのような新興テクノロジーをうまく受け入れられるように、企業文化のさまざまな面を変える責任を自身が負っている」と考えており、6割強のCMOは「利益率を高める責任」、6割弱のCMOは「収益成長を牽引する責任」を担っている。業績の向上に向け「テクノロジーの統合、部門横断的な連携強化の必要性」を認識している。
実際に、部門間連携がうまくできている企業と、そうでない企業とでは、成果に如実な違いが現れているようだ。「社内オペレーションにおいて、部門の枠を越えた連携を十分に実現できていない」と回答したCMOは、2024年に12%の収益成長を報告した一方、「企業全体の運用効率を最適化できている」と答えた先進的な企業のCMOは、13%の成長を報告した。
「このわずか1ポイントの差は、平均年商140億ドル規模の企業にとっては、1億4,000万ドルの潜在的な利益向上に相当」(IBM)しており、軽視できないものであることは明白だ。
インフラ簡素化が急務
データ関連の部門間統合に関して、日本と世界とでは具体的な課題項目に若干の違いがあるものの、多くのCMOが「マーケティング、営業、オペレーションを完全に連携させることで収益が最大20%向上する可能性がある」とみている 。また、6割以上(世界68%、日本61%)のCMOが、マーケティングの技術的なインフラの簡素化が、業務の効率と有効性の向上につながることに同意している 。
IBMのマーケティング&コミュニケーションズ担当シニア・バイス・プレジデントのジョナサン・アダシェク氏は次のように指摘する。
「次の10年で優位に立つ企業は、AIを組織の中核に据え、その上にオペレーティング・モデルとチームを構築し、深く統合していく企業です。多くのCMOに、今のマーケティング・モデルが十分ではないことを認める覚悟が求められます。それがどれほど快適で使い慣れたものであり、変え難いものであっても、もはや必要なものを提供していないばかりか、将来を積極的に妨害しているとすら言えるからです」
目まぐるしい環境変化の中、生成AIを効果的に収益成長に結びつけるには、部門横断的かつ取り扱いしやすいマーケティング・インフラストラクチャーの体制構築が急務になると言えそうだ。
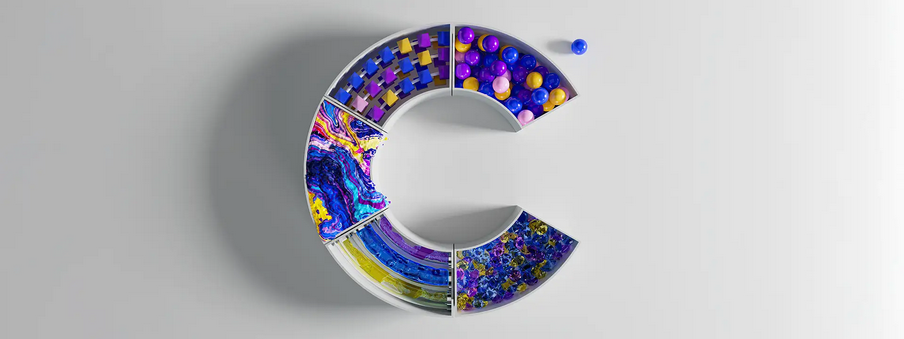




 メルマガ登録
メルマガ登録

