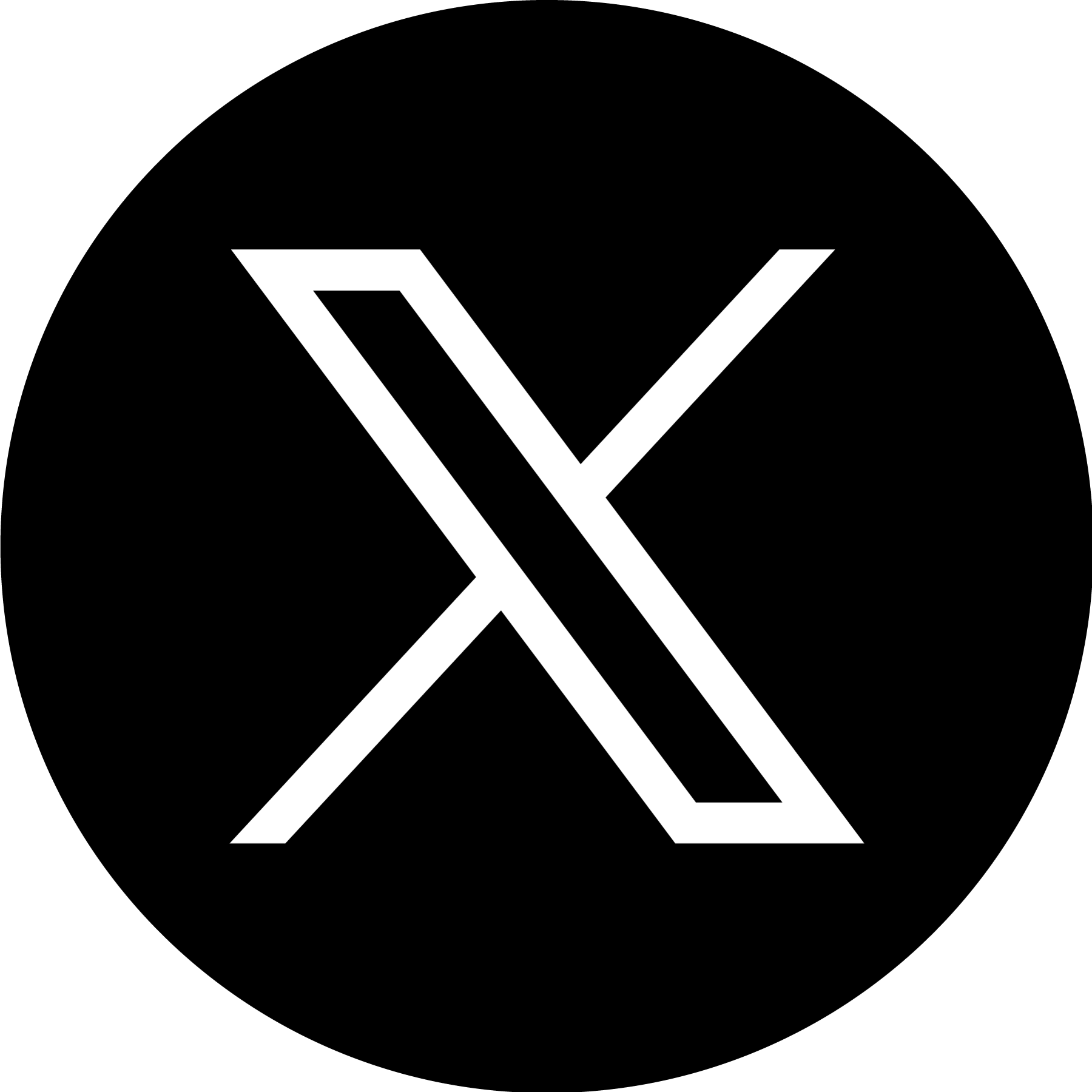RYUKYU note #03
泡盛「残波」が幅広い世代に愛されるお酒になるまでの、親子3代の奮闘
2020/07/16
沖縄県は土地柄や歴史的背景に本土と大きな違いがあることから、ビジネスの進め方も従来の方法では、うまくいかないケースがあります。連載「RYUKYU note」では沖縄で活躍する経営者やマーケターをバトンリレー形式でインタビューし、そのサクセスストーリーの裏側にある秘話や、沖縄ならではの戦略や課題、未来の成長に繋がるストーリーをひも解いていきます。
第3回は、泡盛「残波」を製造販売する比嘉酒造 代表取締役の比嘉兼作氏が登場します。全国から人気を集める「残波」が誕生した背景や、沖縄に数ある泡盛メーカーから売上トップ3に入るほど成長した理由、日本全国で着実に知名度を上げている戦略などを聞きました。
第3回は、泡盛「残波」を製造販売する比嘉酒造 代表取締役の比嘉兼作氏が登場します。全国から人気を集める「残波」が誕生した背景や、沖縄に数ある泡盛メーカーから売上トップ3に入るほど成長した理由、日本全国で着実に知名度を上げている戦略などを聞きました。
戦後の混乱の中、安心安全なお酒として誕生
――「残波」は2018年に70周年を迎えました。どのようにして生まれたのか、歴史を教えていただけますか。
私の祖父母にあたる、比嘉酒造の創業者である比嘉寅吉と比嘉貞子は、ふたりとも学校の先生だったんです。ただ、太平洋戦争が起きて学校どころではないという状況になってしまった。その後、戦争が終わり、物資が何もない状態でお酒の代わりにメチルアルコールを飲んで失明や亡くなってしまう人が後を絶たず、何とかしなければということで地域の人と一緒に安心安全なお酒をつくったのが最初だったと聞いています。
それで泡盛「残波」をつくった当時、読谷村には50軒ほど泡盛の製造会社があったのですが、沖縄が日本に復帰した頃には減ってしまった。しかし、当時の酒蔵は今でいうSDGsを守っていて、お酒を蒸留するために沸かしたお湯を地域のお風呂に使ったり、製造工程で出た蒸留カスを豚のエサにしたり、人々の生活を支えていた。だから比嘉酒造も、その状況を守りたいという想いから一生懸命に取り組んで生き残ってきたんです。

「おとうのお酒」からイメージを刷新
――今では「残波」は日本全土にファンを持つほどの人気ですが、これほど売れるようになったのは、何がきっかけなのでしょうか。
私の父親で2代目の比嘉健が、あまりお酒が飲めない人も楽しむことができる「飲みやすいお酒を提供したい」と蒸留器の改造などに挑戦し、アルコール度数を30度から25度に下げた「残波」を開発したんです。それに2代目は、酒屋の息子なのにお酒が飲めなかった(笑)。だから、そもそも自分が飲めるような、おいしくて飲みやすいお酒がつくりたいと考えたようです。
ちょうど、その頃は1972年前後。つまり沖縄が日本に復帰したタイミングで、沖縄でいうお酒は米国の影響でウイスキーが主流でした。一方で泡盛は度数が高くてお酒臭くて、いわゆる肉体労働者が飲むような“おじいやおとうのお酒”という感覚。古酒が高級レストランに少し置いてある程度で、あとは地域内だけで消費される存在でした。
そこで2代目は、飲みやすい泡盛「残波」を知ってもらうために、沖縄民謡の歌手の前川守賢さんを起用してCMソングをつくりました。これが沖縄の人の耳に残るフレーズで、ラジオから流れる歌声と残波の飲みやすさがリンクしてヒットしたのだと思います。また、1980年代に入ってからは県内にチェーンの居酒屋が増え、それとともに泡盛を飲む市場も少しずつ拡大していきました。

――CMソングは、今でもラジオで流れていますか。
はい「♪泡盛残波~飲んで~ひやるがへい」という歌詞です。この「ひやるがへい」は、意味のないただの掛け声なんです。そこが意外と良かったのかもしれないですね。沖縄は車社会なので、移動中に自然とその言葉が耳に入ってきますしね。
ただ、新しい「残波」を打ち出すときに、飲みやすさや度数の低さはあえてうたいませんでした。というのも、泡盛通の方からは「こんなに薄い酒は、泡盛ではない」というご批判もいただいていましたから。
――とはいえ、「残波」が多くの人に飲まれるようになると、他社も同じように度数を下げた商品を出したのではないですか。
そうです。もともと、ほかのメーカーでも、蒸留器を変えて飲みやすいお酒をつくる取り組みをされていたんです。その中でも、うちは蒸留器のほかに濾過も工夫したり、いろいろな道具を使ったりしながら、他社には真似ができない飲みやすさを研究してきました。

また、25度の「残波」は白いビンなのですが、それまで泡盛のビンは黒や褐色など遮光性のあるものばかり。そのため当時は、見た目がおしゃれという感覚もあったようです。


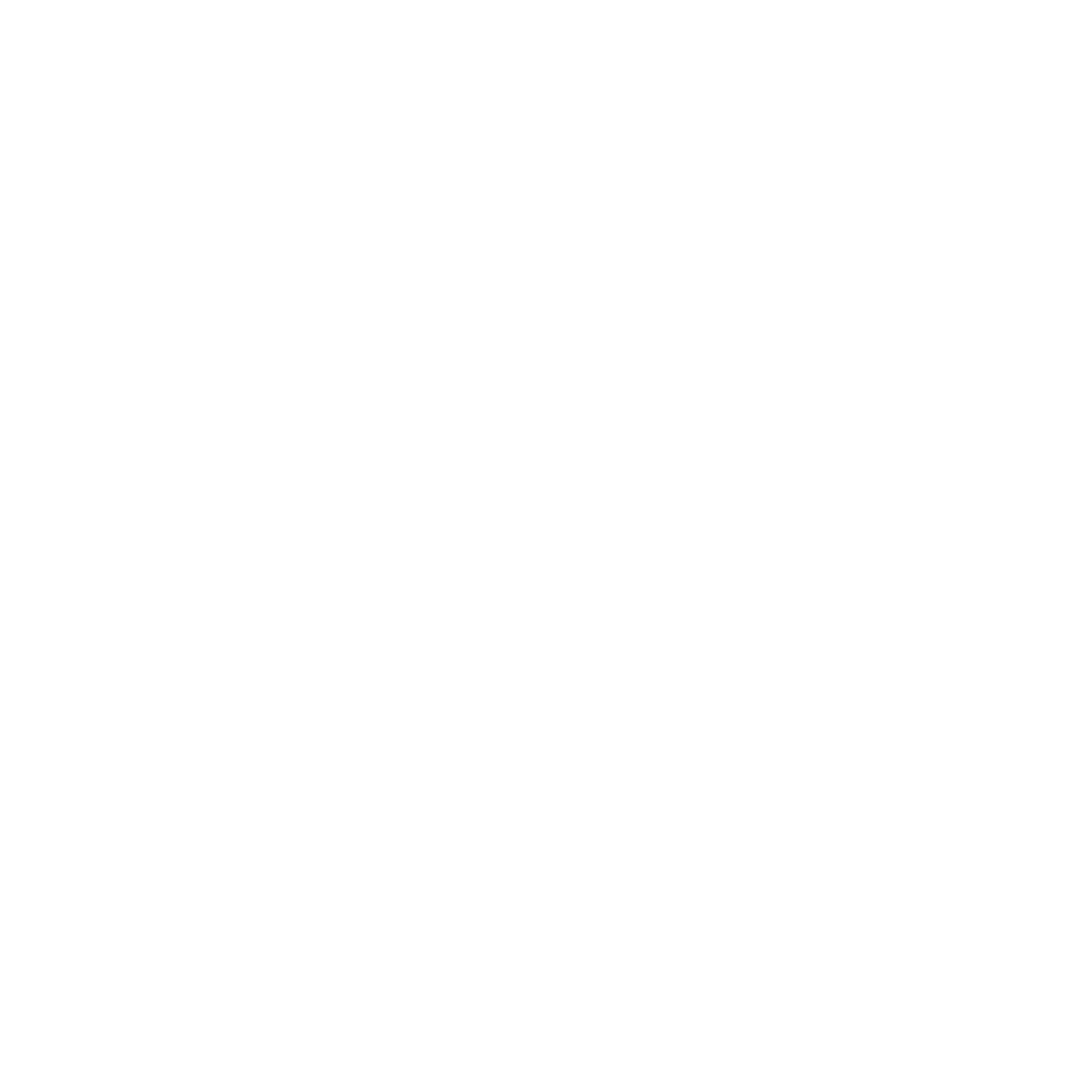

 メルマガ登録
メルマガ登録