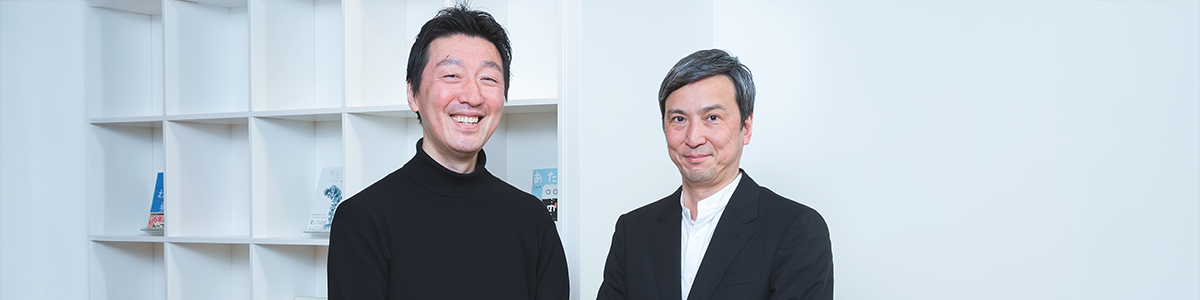新時代のエンタメ舞台裏~ヒットにつなげる旗手たち~ #17
藤井風が示す新時代ヒットの生まれ方と『NHK MUSIC』ブランドに見るNHKのグローバル戦略
2025/03/31
日本の音楽・映画・ゲーム・漫画・アニメなどのエンタメコンテンツが、世界でも注目されることが多くなった昨今。本連載は、さまざまなエンタメ領域の舞台裏で、ヒットを生む旗手たちの思考を noteプロデューサー/ブロガーの徳力基彦氏が解き明かしていく。
今回、徳力氏が対談したのは今年放送開始100年を迎えたNHKで、紅白歌合戦など数々の音楽番組を手がけてきたNHKプロジェクトセンター エグゼクティブプロデューサー 加藤英明氏。テレビ視聴率が低下しストリーミング普及によって音楽業界が激変するなか、国民的音楽番組である紅白やNHKの音楽番組は何を守り、何を変えようとしているのか。
前編では加藤氏が長年携わってきた紅白歌合戦を中心に、そのデジタル活用や唯一無二の価値を創造する取り組みを聞いた。後編では藤井風に象徴される日本人アーティストのグローバルヒットを追った番組づくりや、一種のブランドとも言える「NHK MUSIC」が果たす役割、そしてグローバルに向けてNHKの音楽番組が目指すところに迫った。
今回、徳力氏が対談したのは今年放送開始100年を迎えたNHKで、紅白歌合戦など数々の音楽番組を手がけてきたNHKプロジェクトセンター エグゼクティブプロデューサー 加藤英明氏。テレビ視聴率が低下しストリーミング普及によって音楽業界が激変するなか、国民的音楽番組である紅白やNHKの音楽番組は何を守り、何を変えようとしているのか。
前編では加藤氏が長年携わってきた紅白歌合戦を中心に、そのデジタル活用や唯一無二の価値を創造する取り組みを聞いた。後編では藤井風に象徴される日本人アーティストのグローバルヒットを追った番組づくりや、一種のブランドとも言える「NHK MUSIC」が果たす役割、そしてグローバルに向けてNHKの音楽番組が目指すところに迫った。
「死ぬのがいいわ」が日本語で歌われる
徳力 デジタル化で非常に重要なのは、海外の人に見てもらえることだと思います。日本ではいまだに販売はCDがメインで、ライブは撮影禁止、音楽番組はSNSやYouTubeにアップされないので、海外から見ようとしてもなかなか見られません。日本の音楽業界は世界から見えない活動をしている、日本の音楽は海外では聴かれないと考えてきました。
しかし2~3年ほど前から、どうやら日本の楽曲が海外で聞かれているようだと分かってきます。衝撃だったのは2022年のNHKミュージックスペシャル『藤井風 いざ、世界へ』です。「死ぬのがいいわ」を海外の方々が日本語で歌っているのを観て「こんなことがあるのか」と驚きました。
そこから私もグローバル展開する日本の音楽アーティストに関心を持ち始め、いろいろとリサーチしたり記事を書いたりした結果、昨年末のNHKスペシャル『熱狂は世界を駆ける~J-POP新時代~』でのコメント出演にも繋がりました。実はこの2番組とも、加藤さんが担当されていたんですよね。
加藤 藤井さんのNHKミュージックスペシャルは2021年、2022年の2本は私が担当しました。2021年は日産スタジアムでの無観客ライブの舞台裏に密着し、彼の音楽ルーツを探りました。2本目のテーマは世界に目を向け、YouTubeで弾き語りを始めた藤井さんがどんどん自身の可能性を広げていき、「死ぬのがいいわ」が海外でバイラルヒットを遂げている模様を伝えたいと思いました。しかし、日本に住む私たちにはその実感がありません。
当時はコロナ禍だったので、簡単に海外取材ができませんでした。そこで各国のコーディネーターにリサーチしてもらったところ、彼らの身近やSNSの知り合いに藤井風Loverが大勢いたのです。

NHK メディア総局 プロジェクトセンター 統括プロデューサー
加藤 英明 氏
1997年NHK入局。本部・大阪放送局を経て2004年以降、20年以上に渡りディレクターやプロデューサーとして紅白歌合戦を制作。2011-12年は総合演出、2018-22年は制作統括を務め、現在もプロデューサーとして紅白の企画を担っている。
加藤 英明 氏
1997年NHK入局。本部・大阪放送局を経て2004年以降、20年以上に渡りディレクターやプロデューサーとして紅白歌合戦を制作。2011-12年は総合演出、2018-22年は制作統括を務め、現在もプロデューサーとして紅白の企画を担っている。
徳力 「死ぬのがいいわ」が発表されたのは実は2020年でしたが、2022年夏頃からタイでTikTokユーザーの間でバイラルヒットし、Spotifyなど配信サービスでの再生が急上昇していきました。タイからアジア、欧米に時差的に広がっていったんですよね。
加藤 しかも全て日本語で歌われているにもかかわらず、取材でインタビューした4カ国ほどのファンの方々は歌詞の意味や、藤井さんの伝えたい表現を驚くほど正確に理解しているのです。完全に前例がないヒットのパターンでした。
一方で、自動翻訳機能の発達もあり、米国人が英語以外の曲も聴き始めているというデータはありました。おそらくコロナ禍になって引きこもりがちになるなか、オンラインで藤井さんのような独自の音楽、聴いたことのないような表現に触れたとき、急に世界が広がるという体験をしたのではないか。サブスクリプションサービスによって生まれる新しいヒットの生まれ方を、説得力あるインタビューによって証明できたのではと思っています。
徳力 2024年は世界最大級の音楽フェス「コーチェラ」に5組もの日本人アーティストが出場しました。海外の人たちが「新しい学校のリーダーズ」に日本語でコールアンドレスポンスしたり、YOASOBIの難しいラップを歌ったりしているのを見て、本当に音楽って言語や国境を越えるんだなと実感しました。私も子どもの頃はボン・ジョヴィやマイケル・ジャクソンの歌を、意味も分からずカタカナ英語で歌っていましたが、同じことが逆も起こり得るんだと、本当に衝撃でしたね。
一方、最近のNHKの動きは、それを支援しようとしているようにも見受けられます。2024年10月に放送したNHKミュージックスペシャル『藤井風~登れ、世界へ~』は、なんとNHKワールドジャパンで1年間、英語版のフルバージョンを観ることができます。通常の日本語版が「NHK+」の配信終了と同時に見られなくなってしまうのとは対照的です。
また、NHKでは米国の公共放送NPRの「tiny desk concerts」日本版を制作し、藤井さんやB’zの稲葉浩志さんの貴重なパフォーマンスをNHKワールドジャパンなどで視聴できます。これらはおそらく、海外向けコンテンツとして国内向けとは別の枠組みで制作されているから、このようなことが可能なんだと思いますが、「日本の音楽を世界へ」という意志がすごく感じられます。
加藤 そうですね。日本の音楽業界全体が海外に向いていて、世界に本気で挑みたい日本人アーティストが増えていること、しかも成果を出してヒットしていることを視聴者に伝えるのは、NHKとしての使命と捉えています。
それに加えて、国内の視聴者は減少するなか、我々も海外への発信に目を向けていかなければ発展は見込めません。2025年がNHK放送100年という節目であることもあり、我々も新しい試みとして、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」の授賞式を生中継することを昨年末の紅白で発表したり、海外取材網を生かしたNHKスペシャル『熱狂は世界を駆ける~J-POP新時代』を制作したりといった取り組みを進めています。
そういう意味では、世界を見据えるアーティストや音楽業界と、海外展開を強化したい私たちの思惑が一致していると言えるかもしれません。




 メルマガ登録
メルマガ登録