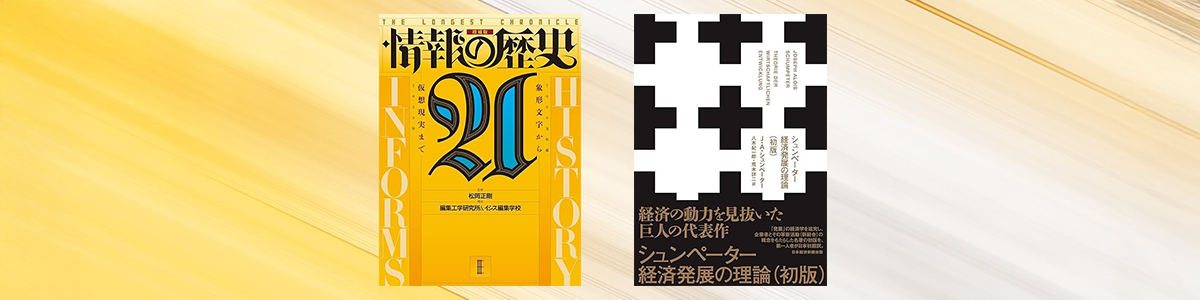【読書の秋】視野が広がった、視座が上がった、視点が増えた1冊 #4
店舗のICT活用研究所 郡司昇氏、花王 廣澤祐氏の「視野が広がった、視座が上がった、視点が増えた1冊」
2025/10/27
昔に比べて短くなった感があるが、だからこそ貴重に思える「秋」。AGENDA Note.では恒例の読書企画として、ビジネスパーソンにトップマーケターが勧めたい本をご紹介する。今年のテーマは「視野が広がった、視座が上がった、視点が増えた1冊」。過ごしやすい季節を最大限活用して、自らの成長につながるお気に入りの本を見つけてみてほしい。
店舗のICT活用研究所/小売DX合同会社 代表/代表社員 郡司昇氏
『情報の歴史21 象形文字から仮想現実まで 増補版』
松岡正剛 (監修)、編集工学研究所
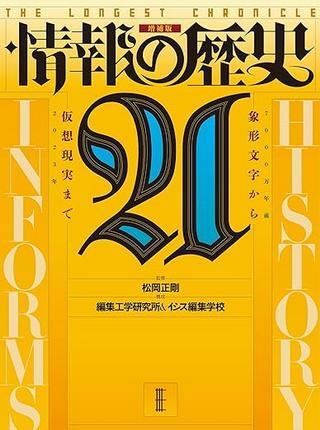
視野が広がったという点で、おそらく読んだ人は少ないであろう松岡正剛監修『情報の歴史21 象形文字から仮想現実まで 増補版』を紹介します。
特徴は人類の誕生から2023年の生成AIまでを「情報編集史」として俯瞰できることです。象形文字の誕生、印刷技術の革新、電話の発明、インターネットの普及、そして現在のAI革命まで、すべてが線でつながって見えてきます。
DXの課題も、この壮大な情報史の文脈で捉えると、全く異なる景色が見えてきます。それは人類が常に情報の新しい形式に適応してきた歴史そのものだからです。
特に印象的なのは、東西5トラックで構成された世界同時年表です。西洋の科学技術発展と東洋の思想・芸術の進歩が同時進行で描かれ、情報がいかに文明横断的に発達してきたかが一目瞭然です。これにより、グローバル化が進む現代ビジネスにおいて、異なる文化圏の情報処理様式を理解することの重要性を再認識させられました。
マーケティングの視点でも大きな示唆があります。生活者行動の変化を単なる「トレンド」として捉えるのではなく、情報技術の進歩に伴う人類の認知様式の変化として捉えることができます。SNSマーケティングの台頭も、口承文化から文字文化、印刷文化、そして今のデジタル文化への連続的な発展として位置づけられます。
増補版では、ウクライナ戦争における情報戦やChatGPTの登場まで含まれており、まさに現在進行形の歴史書として活用できます。ビジネスパーソンにとって、自分たちの仕事が人類の情報史においてどのような意味を持つのかを理解することは、戦略的思考の基盤となります。
花王 デジタル戦略部門 デジタル戦略企画センター 戦略企画部 廣澤 祐氏
『シュンペーター 経済発展の理論(初版)』
J・A・シュンペーター (著)・八木紀一郎 (翻訳),・荒木詳二 (翻訳)、日本経済新聞出版
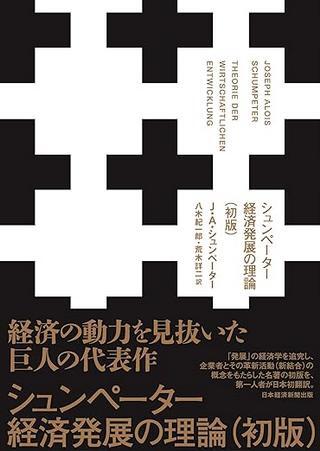
『資本主義・社会主義・民主主義Ⅰ』『資本主義・社会主義・民主主義Ⅱ』
ヨーゼフ・シュンペーター (著)・大野一 (翻訳)、日経BP
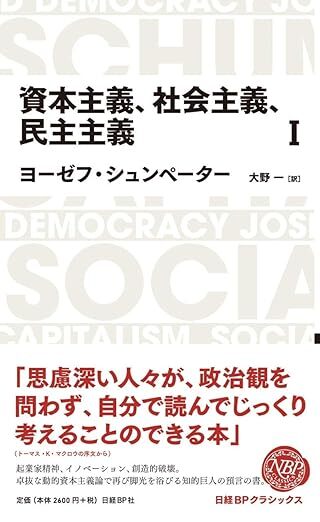
「視野が広がった、視座が上がった、視点が増えた1冊」という今回のテーマに対し、私はヨーゼフ・シュンペーターの『経済発展の理論』と『資本主義・社会主義・民主主義』の2冊を比較して読むことを推薦します。
なぜなら、この2冊を読み比べ、時代の変化と各書の主張や重視点の違いを読み解くことによって、初めて、現代を生きるビジネスパーソンにとって不可欠な「視座」と「視点」が得られるからです。
「イノベーション」という言葉は、ビジネスシーンで頻繁に用いられますが、その本質を捉えられているでしょうか。この言葉の根底にあるシュンペーターの「新結合」(=既存の知や資源の新しい組み合わせ)という概念やその論理を知らないままに、気軽にイノベーションという言葉を使うビジネスパーソンが多いのではないでしょうか。
『経済発展の理論』は、日々の業務に対する見方について、単なる戦術や作業ではなく、「新結合」によって新たな価値や仕組みを生み出す営みとして、その本質を見つめ直すきっかけを与えてくれます。
さらに重要なのは、1912年の前著と1942年の後著との比較です。前著ではイノベーションの担い手は熱意と行動力のある企業家という個人に軸足が置かれていたのに対し、30年後の後著では、その主体は大企業の組織的研究開発へと変わります。
この主張の変化の背景にある前提や、彼が後年に描いた社会の停滞感は、あらゆるカテゴリーが成熟しコモディティ化の進む現代社会とリンクする部分も多いと言えます。
実際、2025年10月13日にスウェーデン王立科学アカデミーから発表された今年のノーベル経済学賞は、シュンペーターが提唱したイノベーションの論理について実証的なアプローチから再検討を行い、「イノベーション主導の経済成長の解明」に貢献したとして、米ノースウエスタン大のジョエル・モキイア教授と仏コレージュ・ド・フランスのフィリップ・アギヨン教授、米ブラウン大のピーター・ホーウィット教授の3氏に贈られました。このことは、シュンペーターの主張が、100年以上前に生み出された古典でありながらも、その効用は現代でなお色褪せず、むしろ重要性が増していることの証でもあります。
推薦図書の2冊は、社会と経済、個別の事業活動の相互作用やその動態を理解するための「視座」を与えてくれます。変化の本質を古典から学ぶことで、現代社会への洞察力と、未来の構想力に対する「視点」が増えるでしょう。
※編集部注:記事内で紹介した書籍をリンク先で購入すると、売上の一部がアジェンダノートに還元されることがあります。




 メルマガ登録
メルマガ登録