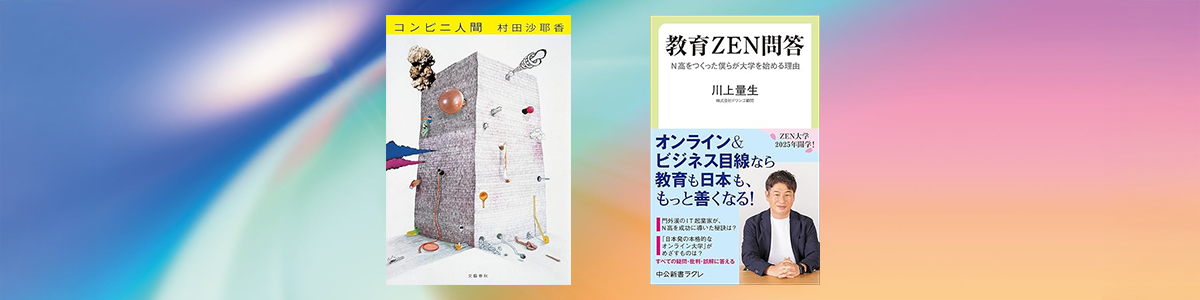【読書の秋】視野が広がった、視座が上がった、視点が増えた1冊 #5
カンロ 内山妙子氏、近畿大学 世耕氏の「視野が広がった、視座が上がった、視点が増えた1冊」
2025/10/29
昔に比べて短くなった感があるが、だからこそ貴重に思える「秋」。AGENDA Note.では恒例の読書企画として、ビジネスパーソンにトップマーケターが勧めたい本をご紹介する。今年のテーマは「視野が広がった、視座が上がった、視点が増えた1冊」。過ごしやすい季節を最大限活用して、自らの成長につながるお気に入りの本を見つけてみてほしい。
カンロ 常務執行役員 マーケティング本部長 内山妙子氏
『コンビニ人間』
村田沙耶香 (著)、文藝春秋
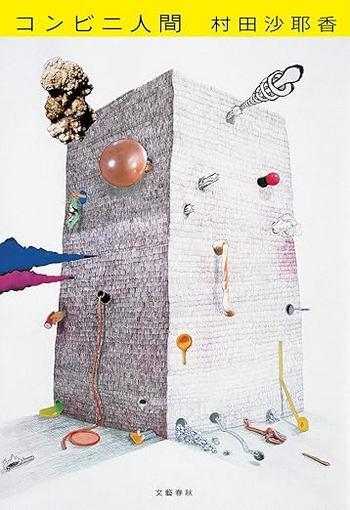
普通に生きられないコンビニ店員の主人公がマニュアル通りの世界で安定を見出す
「社会の常識」と「自分らしさ」の境界を問う作品です。
まず、主人公の特異性にガツンとやられます。
幼い頃、校庭で死んだ鳥を見つけた主人公は、悲しむ同級生を見て
「そんなに悲しむなら、食べれば無駄にならないのに」と考え
焼鳥が好きなお父さんに持って帰ろうと提案して皆にドン引きされます。
読み進むにつれて、なるほど主人公は感情ではなく合理で世界を理解しようとする人間なんだなとわかり、そういう目線で見ると普通ではないことがマイナスではなく個性に映ります。
が、とうてい理解できない周辺の人たちに普通じゃないと言われ続けた結果、
妹や同僚、友達といった「普通の人」を観察し、その口調や髪型、服装を真似ることで「普通の人」を演じる生存戦略を選択します。
個性を捨てたのにどう考えても普通じゃない。生存戦略は失敗じゃないかと思うのですが、
最後、主人公は自分にとっての幸福は「○○○○」と明言して終わります。
終始、普通や適合といった自分の中の社会的価値観を揺さぶられながら読んだ作品でした。
マーケター視点で考えると『コンビニ人間』は「共感力」を鍛えるというより、
「常識を疑う力」を鍛える本だと言えます。
顧客も人間も平均ではなく個である、というペルソナや共感設計にも一役買えそうな作品です。
一人ひとりの異質さにこそ、世界を変える種がある。
マスと個をみつめるバランスをもう一度考えたくなる1冊でした。
近畿大学 常任理事/経営戦略本部長 世耕石弘氏
『教育ZEN問答 ― N高をつくった僕らが大学を始める理由』
川上量生(著)、中央公論新社
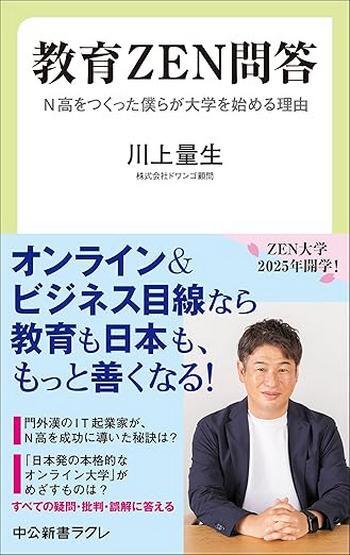
2016年に通信制のN高校が開校した際、多くの教育関係者は「わけのわからない名前で、ネットで授業など」と冷ややかな目を向けていたことを覚えている。だが私は、当初からその成功を確信していた(決して後付けではない)。なぜなら、あのドワンゴの川上量生氏が本気を出していたからである。結果として、N高は短期間で日本最大の高校へと成長し、次なる挑戦は大学設立へと続いていった。
本書はそうした著者の問題意識と実践を率直に描いた1冊だ。N高の立ち上げ、運営上の葛藤、そしてZEN大学構想へ至る経緯は、大学で通信教育にも携わる私にとって非常に刺激的である。全くの異分野でありながら、「理屈っぽいイデオロギーを振りかざす人が多い」教育業界において、その矛盾を突いたアイデアで拡大していくストーリーには、どの業界においても新たな境地を拓こうとする人々にとって多くの示唆がある。
本年、近畿大学でもN高の成功に可能性を感じ、通信制による新たな建築学部を立ち上げた。初年度からすでに1700人が入学している。我々も川上氏と同じく、教育界に新たなムーブメントを起こしていきたい。
※編集部注:記事内で紹介した書籍をリンク先で購入すると、売上の一部がアジェンダノートに還元されることがあります。




 メルマガ登録
メルマガ登録