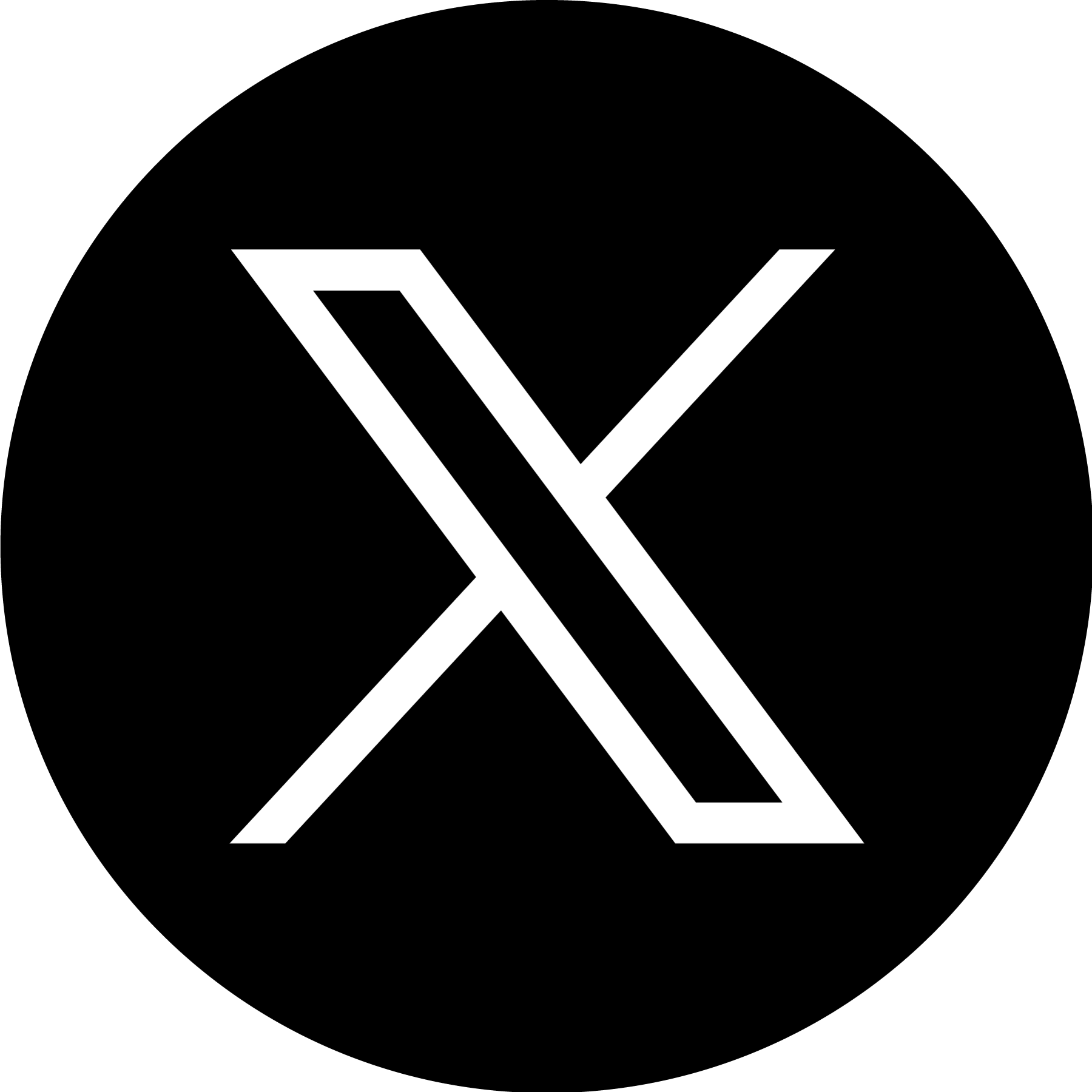マーケターズ・ロード 富永朋信 #04
「ところで、その人の靴は舐めましたか」 僕が三枚目のデブキャラにシフトした理由 【イトーヨーカ堂 富永朋信】
3度目の正直でCCJCに入社
ウェブ・ティービー・ネットワークスで「WebTV」事業が終了することになったタイミングで転職活動を行い、得たオファーは、デル、日本コカ・コーラ(CCJC)、ナスダック・ジャパン、ジャパン・エントリーの4社でした。もちろん日本コカ・コーラ(CCJC)を選びました。めちゃくちゃ嬉しかったですよ。何しろ3度目の正直ですからね(笑)。2001年、31歳のときのことです。

最初に配属されたのは、「e-ベンチャー」。のちに「マーケティングベンチャー」に名称変更されましたが、CCJCの中で「何か新しいことをする」というミッションを持つ部門でした。
配属されて最初に与えられたミッションは、「携帯電話を使って何かやること」そして「自動販売機をどうにかすること」。当時、自販機は日本全国に200万台設置されていて、うちおよそ半分がコカ・コーラ社です。
コカ・コーラにとって、自販機はとても重要な顧客チャネルです。ブランドの成功要因の相当な部分を、自販機が占めていると言っても過言ではないでしょう。そんな自販機の売上やプレゼンスが、コンビニやスーパーの台頭で下降している状況でした。

こうした中、自販機とiモードを連動させて、新しい何かを創造しようというプロジェクトが立ち上がったのです。これが2002年、CCJC、エヌ・ティ・ティ・ドコモ、伊藤忠商事の3社による新サービス「Cmode(シーモード)」として発表されます。
これは、なかなかロマンティックなアイデアでした。というのも、自販機は一度設置したら動かないので、CRMならぬ「LRM(ロケーション・リレーテッド・マーケティング)」的な施策がいろいろと考えられます。
例えば、近くに映画館があるロケーションなら、自販機で映画のチケットを販売することができる。近隣の飲食店で使えるクーポンを、自販機で出力することもできる。あるいは、当時は定額課金制がほとんどだった着メロや待ち受け画面などの携帯コンテンツを自販機でバラ売りすることもできる。そんな多様な可能性を持ったプロジェクトでした。
仕事のスタイルを変えるきっかけとなった、ある一言
上司は、電通出身の佐藤真さんでした。彼はクリエイティビティの塊で、天才的なアイデアマンだった。僕も面白いアイデアを思いつくほうだという自信があったのですが、彼にはまったく歯が立たなかったですね。CCJC時代を語る上で、佐藤さんとのエピソードは欠かせません。
頭が抜群に切れる佐藤さんは、どんなときでも一筋縄ではいかなかった。一生懸命につくった提案書を見せても、「こんなのは、ダメです」「意味がわかりません」と、ことごとく却下・否定されました。いままで経験した2社では「こんなものでいいか」と何となくごまかしてきたことが、全く通用しなかったのです。
演繹的なロジックでストーリーを組み立てることで、戦略に強い説得力を持たせることができるということ。メッセージには順番があり、それを間違うとミスリードしてしまう可能性があること。ひとつのストーリーに最低でもひとつのアイデアが含まれていないと、人の心は掴めないということ。そうした数々のことを、佐藤さんから死に物狂いで学び取る日々でした。
また、仕事における自分のスタイル・スタンスを変えるきっかけになった出来事もありました。Cmodeのプロジェクトの進行中、僕はドコモ側の責任者の方と話が合わず、物事が思うように進まないことに困り果てていました。
そんな折、佐藤さんが「どうしたんですか、富永さん」と声をかけてくれた。それで、かくかくしかじかと説明したところ、佐藤さんにこう言われたんです。
「それは、さぞかしお困りでしょうねえ。ところで富永さん、その人の靴は舐めましたか?」
まるで雷に打たれたような衝撃を受けました。

これまで僕は、コカ・コーラ側の理屈や自分のやりたいことを、ドコモ側の事情や要望を顧みることなく、「これが正しいのだ」と言わんばかりに押し付けていたわけです。それでは、衝突するに決まっています。
佐藤さんは「もっと相手の懐に飛び込む気持ちでやれ」というメッセージを、「靴を舐める」という強い言葉に込めて投げかけてくれたのです。
もし、もっと普通の言い方をされていたら、反発してしまっていたかもと思うのですが、衝撃的な表現だったからこそ、自分の弱さに気づくことができました。
それまでの僕は、賢いことが一番、頭が切れることが一番だと思っていました。しかしビジネスの現場では、それが大して役に立たないこともあると教えられました。事を成すためには、ときに「靴を舐める」ことも必要。
そう気づかされ、僕は“キレキレ”キャラをやめて、“三枚目のデブキャラ”にシフトチェンジしたのです(笑)。
驚いたことに、実際、やり方や態度を変えたことで、ドコモ側とも上手くいくようになりました。この気づきがあったからこそ、Cmodeプロジェクトを、真の意味で3社共同プロジェクトとして進めていくことができたようにも思います。


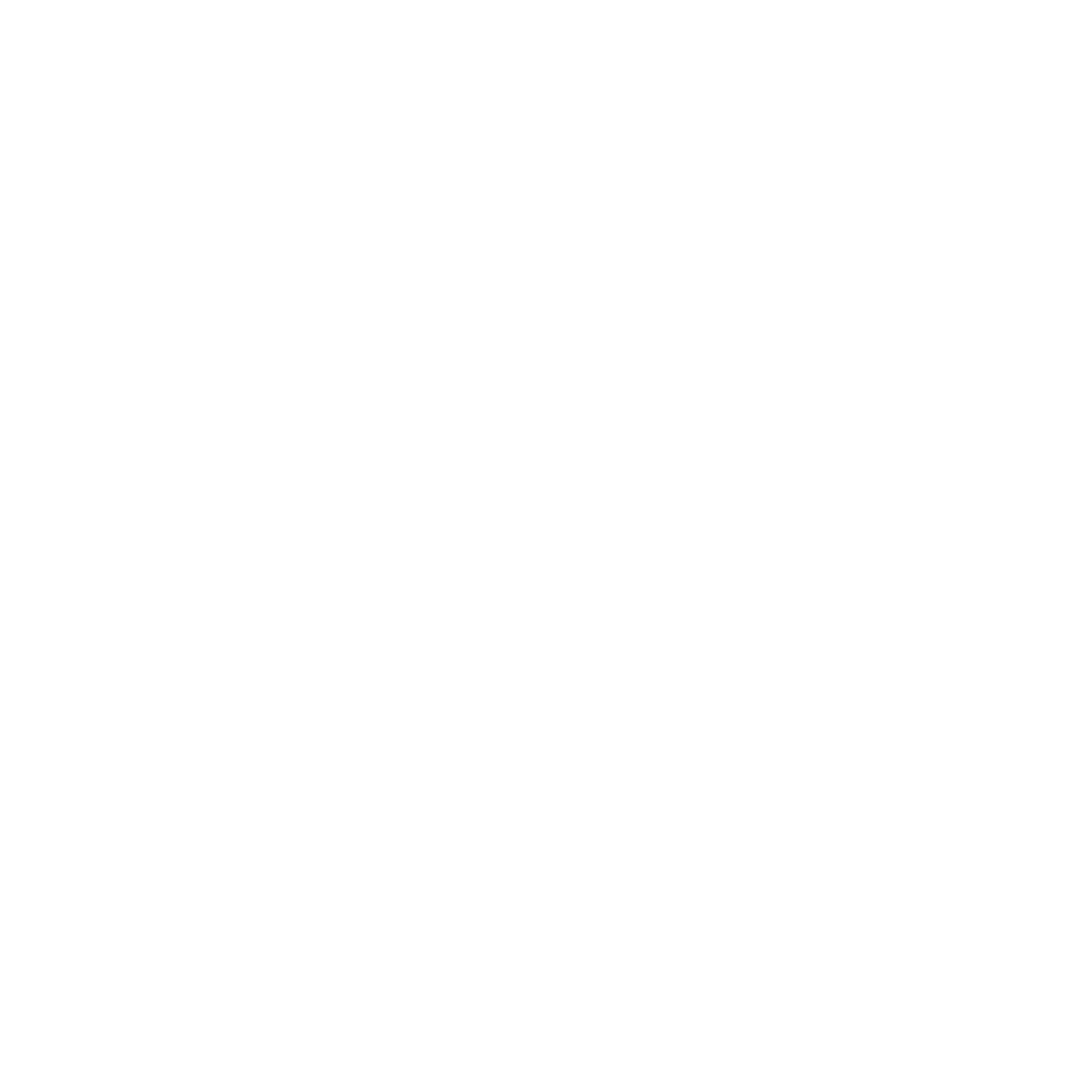

 メルマガ登録
メルマガ登録