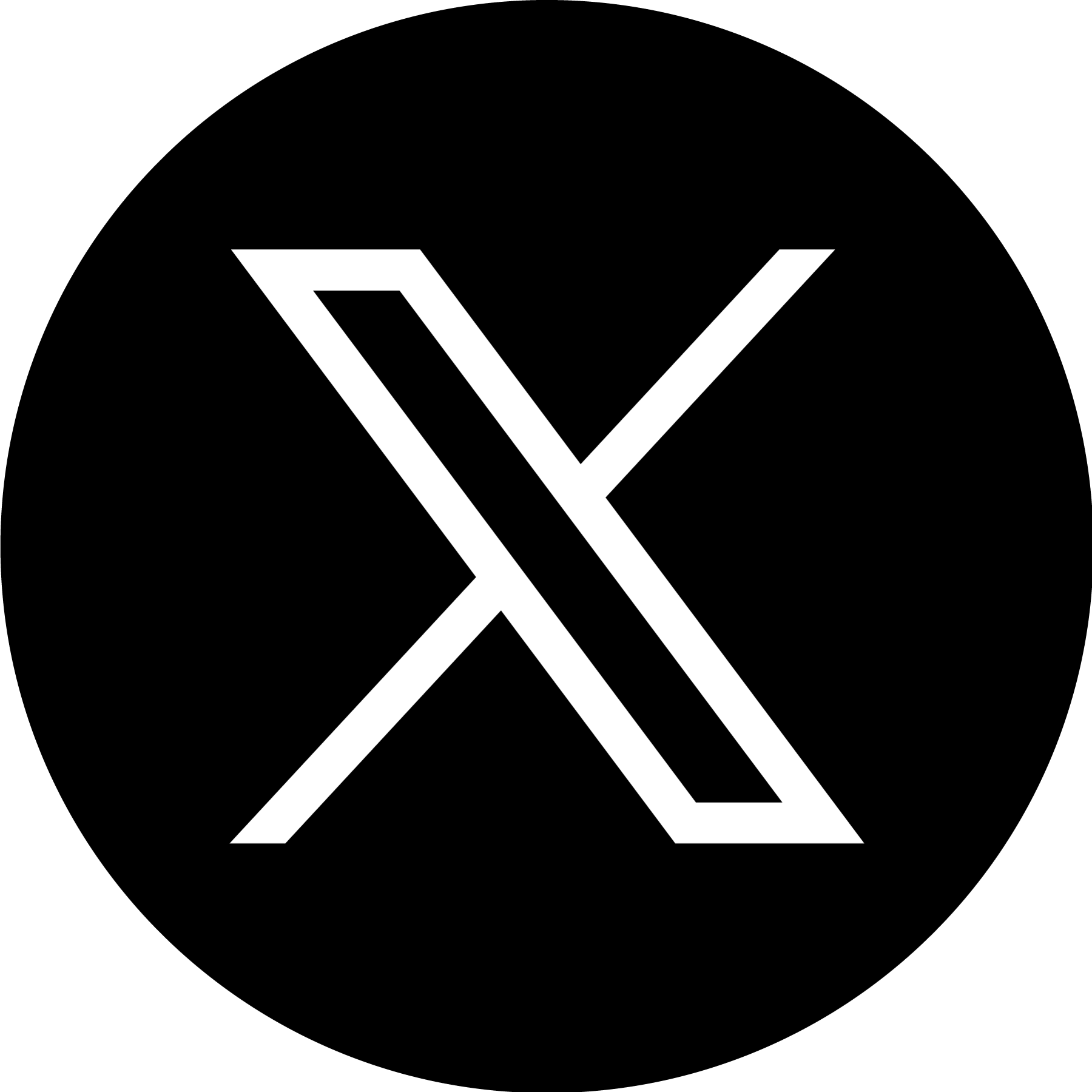マーケティングは、どこまで人間を理解できるのか #04
伝統的な消費者行動モデルの呪縛を解くために、マーケターは「注意」の見方を変えよう
2020/10/01
「注意を引きたい」とは言うけれど
日々の生活のなかで、消費者の脳には膨大な量の情報が絶えず入力されています。しかし、人間の脳の処理容量には大きな限界があり、入力情報の大半は処理されずに忘れ去られます。
そのため、自社の商品・サービスや、それに関わる広告コミュニケーションを、しっかりと消費者に届けて処理してもらうことは、マーケターにとって、とても重要かつ難しいタスクと言えます。
実際、私も消費者の注意を引くための相談を受ける機会がとても多いです。「テレビCMで目立つにはどうすれば」や「もっと店頭でパッケージを見てもらうためには」など。
これらの質問を本当によく受けるのですが、実は個人的にはすごく違和感があります。なぜなら、それならば単純に黒板を爪でひっかいている映像と音を流せばいいじゃないですか。
でも、そう回答すると、「いや、そういうことじゃない」と怒られます。当然ですよね。そこで続けて、「では、どういうことですか?」と相談の意図を深掘りすると、「まずは商品を知ってもらうことが大事で・・・」と、口ごもって会話が続きません。あるいは、もっと悲しいケースでは、「上司がそう言うんです」「KPIだから」ということもあります。
そうならば、やはり「黒板を・・・」となるように思います(ならないですか?)。

呪縛を解き放ち、別の視点から考えよう
この妙な会話の原因は、前回のコラムで強調したことと同様で、マーケターが直感的に抱く消費者像や、100年以上続く消費者行動のモデルの呪縛にあると考えています。
つまり、消費者の意思決定に至るまでの流れを段階的に捉えて、まず商品やサービスに気付いてもらって、知ってもらい、そこから熟考して答えを出してもらうと想定しているんです。そのため、最初に注意を引くことが必要だと考えるのです。

いったん、その段階的なモデルは忘れましょう。
最近、注目されている行動経済学の事例などを見ても、多くの場合、消費者が順を追って考えて意思決定しているわけではないことは明らかです。そのことは、前回のコラムでも考察しました。
消費者は、広告コミュニケーションにさらされると、その脳内では、商品の名前や色、形、過去の体験、そのときの部屋や消費者自身の心理的状態などの文脈、その他諸々まで、無数の情報が瞬時に、そしてほぼ同時に処理されているのです。
おそらく、それと合わせて感情の反応も生じ、それが後の意思決定やアクションに大きく影響します。
そのため、「注意を向けてもらう」や「知ってもらう」ということを、この一連のプロセスから切り離して考えるべきでないし、そもそもできないはずです。だからこそ、いくら注意を引くとはいえ、「黒板と爪」の提案は受け入れられないんです。


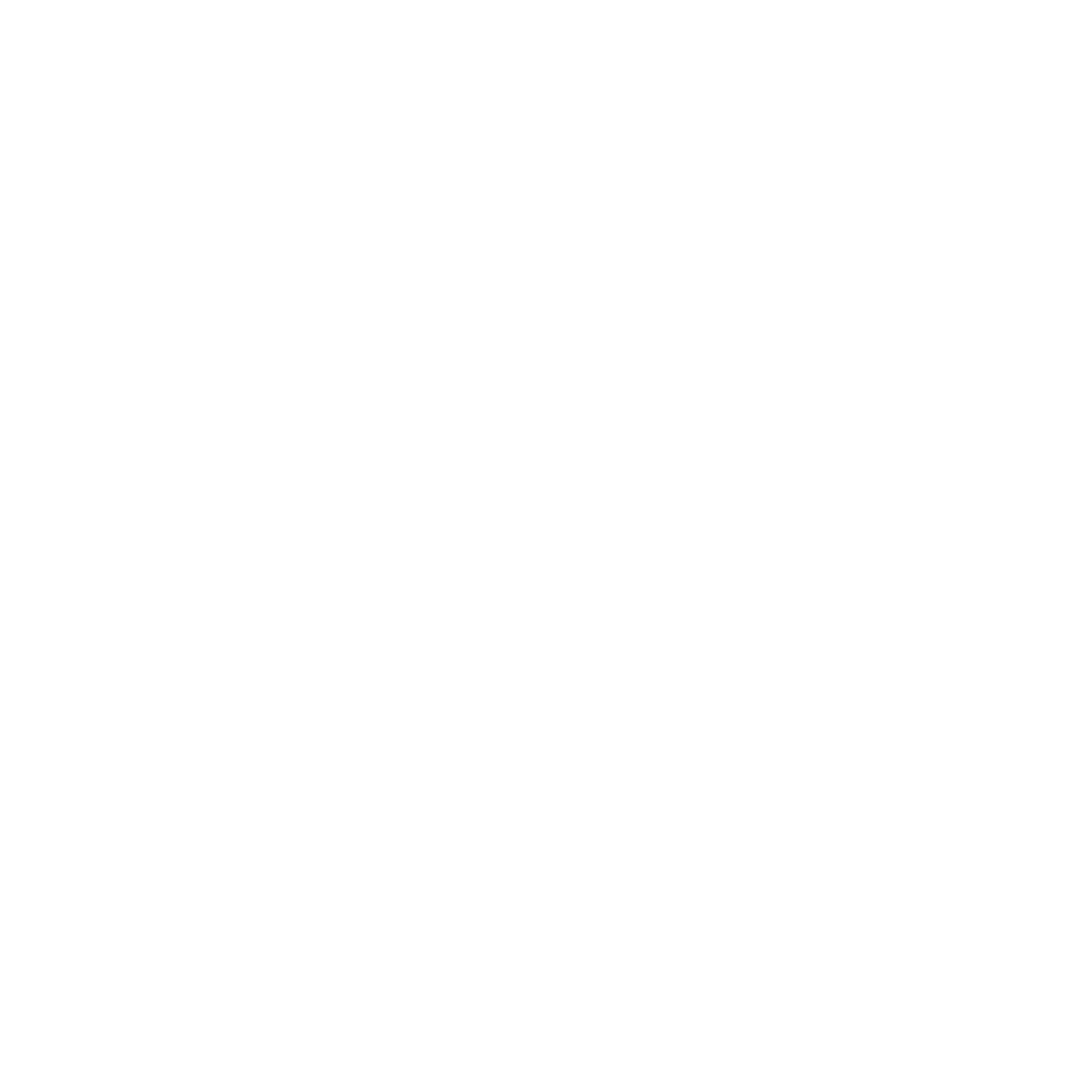

 メルマガ登録
メルマガ登録