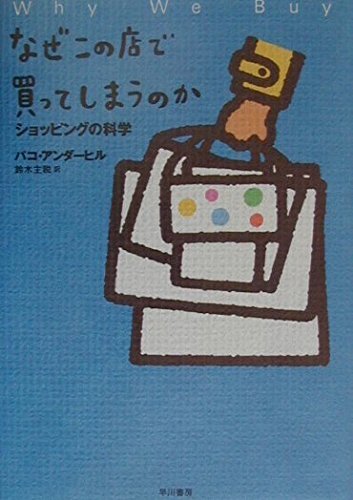社会変動を紐解き、マーケティングで時代を拓く #03
時間シェア争奪の時代、マーケターは「欲求」の迷路を解いて活路を開く【LIFULL篠崎亮氏】
不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)」を運営するLIFULL(ライフル)で、住生活に関する不動産会社や自治体のマーケティング・課題解決支援に取り組む篠崎亮氏が、時代の変化に伴う消費者や商品・サービスの動向を読み解き、未来を拓くマーケティングのあり方を模索する本連載。
消費行動は言うまでもなく、人間の欲求を叶えるためのものである。では、商品が消費されていれば欲求に応えられているのか? この問いは、消費促進を担うあらゆるマーケターにとって重要だと篠崎氏は指摘する。第3回の本稿では、消費者の生活環境や日常行動の変化を捉え、ますます複雑化する人の欲求を考察していく。
消費行動は言うまでもなく、人間の欲求を叶えるためのものである。では、商品が消費されていれば欲求に応えられているのか? この問いは、消費促進を担うあらゆるマーケターにとって重要だと篠崎氏は指摘する。第3回の本稿では、消費者の生活環境や日常行動の変化を捉え、ますます複雑化する人の欲求を考察していく。
「サービス利用」が「商品利用」を上回る時代
マーケターは担当する商品の売れ行きの調子が良いときに、なぜ消費されているかを事業の内部環境・外部環境の変化とともに正しく把握できていなければ、ある日、商品のライフサイクルが下り坂を迎えたときに手の打ちようもなく時代に取り残される危険を招きます。実際、長年マーケティングに携わるなかでヒット商品や時代のトレンドと呼ばれるものが不調に陥り、忘れ去られていく姿を何度も見てきました。
そして、人の欲求とは多岐にわたって迷路のように入り組み、俯瞰と実感を繰り返して理解しようと努めないと掴めません。逆に、消費者がどのような生活環境にいて何を思って行動しているのかに、どうやって向き合うかマーケターが普段から考えておくことは、窮地に立つ事業を救うヒントにもなります。

LIFULL / LIFULL HOME’S事業本部 マーケティング部 クライアントマーケティングユニット コミュニケーショングループ・グループ長
篠崎 亮 氏
2020年LIFULLに入社。不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」のブランドリニューアルプロジェクトのプロジェクトマネージャーを担当。その後、BtoBマーケティングの専門部署を立ち上げ、グループ長として不動産会社・自治体など住生活に関わる事業者の事業支援・課題解決を管掌。以前は、外資広告グループ・Interpublic Groupのブランディングエージェンシーや国内の広告代理店でストラテジックプランニングディレクターとして、商業・流通ビジネス、消費財メーカー、カメラ、スポーツメーカー等の大手クライアントのマーケティング支援や広告コミュニケーションを担当。
篠崎 亮 氏
2020年LIFULLに入社。不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」のブランドリニューアルプロジェクトのプロジェクトマネージャーを担当。その後、BtoBマーケティングの専門部署を立ち上げ、グループ長として不動産会社・自治体など住生活に関わる事業者の事業支援・課題解決を管掌。以前は、外資広告グループ・Interpublic Groupのブランディングエージェンシーや国内の広告代理店でストラテジックプランニングディレクターとして、商業・流通ビジネス、消費財メーカー、カメラ、スポーツメーカー等の大手クライアントのマーケティング支援や広告コミュニケーションを担当。
財務省が公表した2022年の貿易収支(輸出額から輸入額を引いた額)は19兆9713億円の赤字となり、2023年までで赤字は3年連続です。かつて日本は「輸出大国」として巨額の貿易黒字を積み上げましたが、近年は資源価格の高騰と円安が重なって貿易赤字が続いています。商品の海外生産が進むことで技術が平準化されて差別化が難しくなるなかで、世界的に支持を得たのはGAFAといった米国のIT(情報技術)プラットフォーマーでした。
Amazonでの買い物もスーパーでの買い物も、同一の商品を買えば、結果的に商品を通して叶う欲求は一緒です。買い物の最中に抱く、その商品を手にして叶えたい姿は近しく思います。しかし、当然ながら顧客体験(CX)は違います。複数の商品を組み合わせながら未来を想像する楽しさ、買い物カゴに商品を入れて自分の欲求を確認すること、決済によって自分へのご褒美を形にすることなど、その時々の「サービス利用」の欲求に適した流通チャネルから、人は商品を手にしようとします。
買い物において、後から「なんでこんなものを買ってしまったんだ」と思う体験は誰にでもあると思います。「衝動買い」自体は歴史も古いですが、2019年にGoogleが提唱した「パルス型消費」は、これまで知らなかった商品を買うことに躊躇しないという特徴もあり、「サービス利用」そのものへの欲求が、商品のブランドへの信頼関係を上回って、人々を決済へと導いていると捉えられます。
※編集部注※
パルス型消費行動: Googleが提唱した新たな消費行動の概念。ある程度時間をかけて購入する従来の「ジャーニー型消費行動」と区別し、スマートフォンやECサイトの普及を背景とした瞬発的な消費行動を指す。非日常的な「衝動買い」よりも日常的で、特定の意図を持たない情報収集から開始される場合が多いことなどを特徴とする。
2001年に刊行されたパコ・アンダーヒル著の「なぜこの店で買ってしまうのか」(早川書房)はショッピングの科学を解説していて、私も20~30代にかけて商業施設のマーケティングに携わる中で参考にしてきました。しかし本書が、意思決定をつかさどる感化的な要素としてショッピングの鍵は「感触と試用」にあると説いているのに対して、昨今の「パルス型消費」は直感といった感覚は重視されているものの、情報の刺激だけで消費判断がされるように時代は変化したとみることもできます。
アプリ分析サービスのApp Apeがまとめた「アプリ市場白書2022」によると、1ユーザーあたりの日間平均アプリ利用時間は4.8時間に上ります。カテゴリー別に見るとエンタメ系や動画系、そしてゲーム系の利用時間が多く、Z世代に至っては1日のアプリ利用時間の平均は6時間39分で、動画アプリに92分、SNSに90分となっています。
仮に8時間を睡眠として、起きている時間を16時間、そのうち8時間を仕事や勉強にあて、6時間をモバイルアプリに使えば、他の時間消費は1日2時間あれば良い状況です。生活に必要な食事や入浴の時間を入れれば、ほとんど隙間は残らないでしょう。
モノの売れない時代、といった言葉もありますが、この時間消費の中で顧客に自社の商品と向き合ってもらって、欲求に応えられることを時間を割いて理解してもらい、購買を引き起こすことはどこまで可能でしょうか。顧客自身も、購買前に商品を試用して感触を確かめて、本当に叶えたい姿をイメージできているのでしょうか。特に住まいや車といった高価で付加価値性も高く、検討にしっかり時間を使う必要がある消費も、時間シェアをモバイルアプリから奪うのはハードルが高くなっていると言えるのではないでしょうか。




 メルマガ登録
メルマガ登録