昔に比べて短くなった感があるが、だからこそ貴重に思える「秋」。AGENDA Note.では恒例の読書企画として、ビジネスパーソンにトップマーケターが勧めたい本をご紹介する。今年のテーマは「視野が広がった、視座が上がった、視点が増えた1冊」。過ごしやすい季節を最大限活用して、自らの成長につながるお気に入りの本を見つけてみてほしい。
Mizkan 代表取締役専務兼日本+アジア事業COO 槇亮次氏
『孫正義 300年王国への野望』
杉本貴司 (著)、日本経済新聞出版
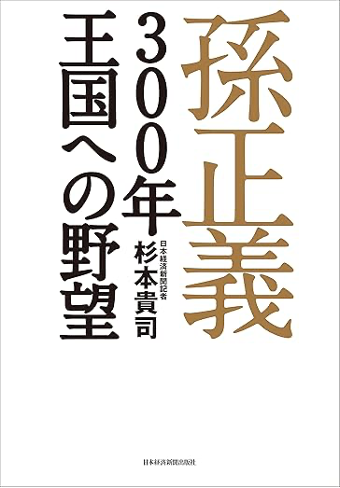
今回のテーマにドンピシャと思った1冊です。
タイトルから孫正義ソフトバンクグループ会長の立志伝のように映るかもしれませんが、内容は成功譚の域を超えて、永続的に続く組織をつくるための群戦略と同志的結合について丁寧な取材と事実検証に基づいて講じられています。
企業とはそもそも何のために存在するのか?
何のために人は働くのか?
そんな本質的な問いが突きつけられます。日々、「今年の利益目標は?」「今後5年でこれぐらい成長しよう」と短い尺で物事を見て、そして振り回されているのは私だけではないのではないでしょうか。
この本に出会うまでは「ソフトバンクはなぜ30年ビジョン、300年ビジョンと長いスパンで話をするのか?」と疑問に思っていました。読了後、当時預かっていた(前職の)ネスレの菓子事業で20年後を見据えたビジョンづくりを進め、その後、創業220年超の歴史を持つMizkanに転じ、「創業300年に向けて何を成すべきか?」と自分の使命を問う日々を迎えることになりました。
企業の存在意義、人が働き生きる意味。そんなことを自然と考えてしまう名著です。
リクルート マーケティング室 クリエイティブディレクター/部長 萩原幸也氏
『「頭がいい」とはどういうことかーー 脳科学から考える』
毛内拡 (著) 、筑摩書房
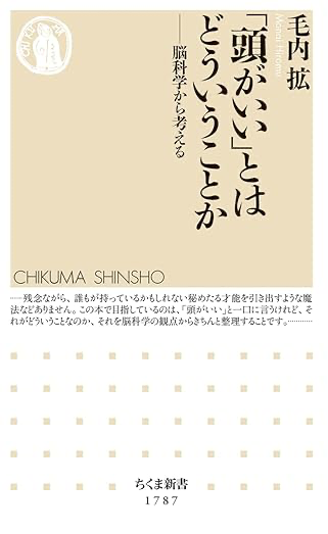
皆さんは、脳にある「グリア細胞」をご存じでしょうか。よく「脳は10%しか使われていない」と言われますが、これはニューロンに対してグリア細胞が9倍ほどあるからできた言説と言われています。それほど、グリア細胞は「神経細胞を支えるだけで、ほとんど働きがない」と考えられてきました。しかし近年はその重要な役割が次々に明らかになっていると。
かつて役に立っていないと思われていたものが、実は重要だった ーーそんな展開は胸が躍りますね。
それはさておき、本書では、能力を発揮し続けられる人とそうでない人の違いを、脳科学の観点から解き明かします。「頭がいい」とは、IQや記憶力だけでなく、感覚や運動能力、アートや創造性、他者の気持ちを理解する力なども含むと捉えます。そして、それらがどのような仕組みで高まるのかを、グリア細胞の知見も踏まえて解説していきます。
そんな本書の著者・毛内 拡さんに取材した記事も公開しています。ぜひご覧ください。
AI時代における「頭がいい」とはどういうことか? 気鋭の脳科学者・毛内拡氏に聞く(アジェンダノート)
この記事中で毛内さんも述べていますが、人間が自分自身を知るには、脳科学は必須科目です。マーケティングは人に向き合う仕事。人間理解のために、ぜひご一読ください。
※編集部注:記事内で紹介した書籍をリンク先で購入すると、売上の一部がAgenda noteに還元されることがあります。




 メルマガ登録
メルマガ登録

